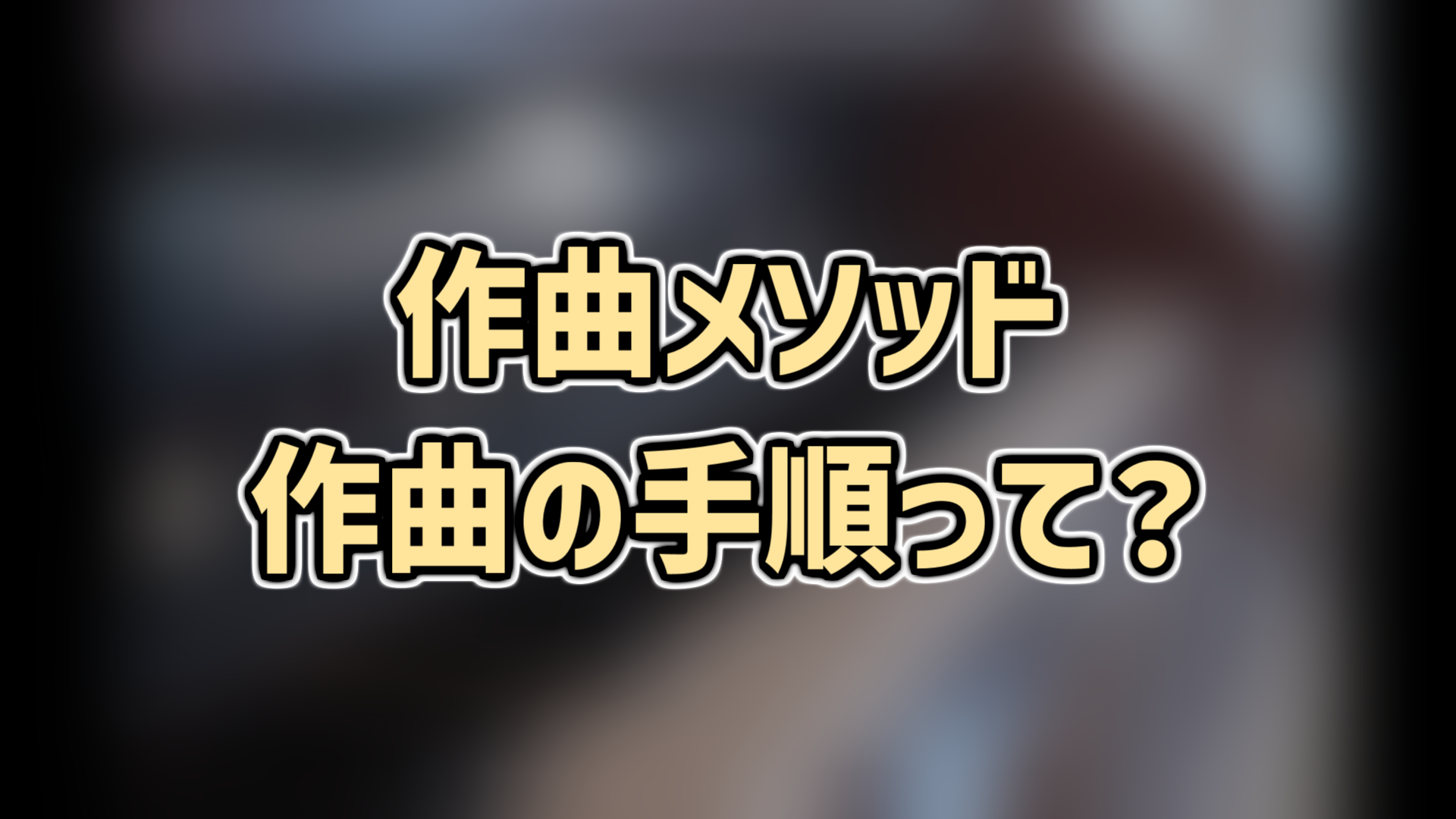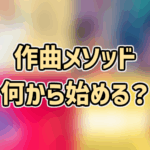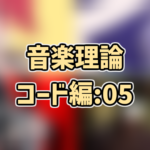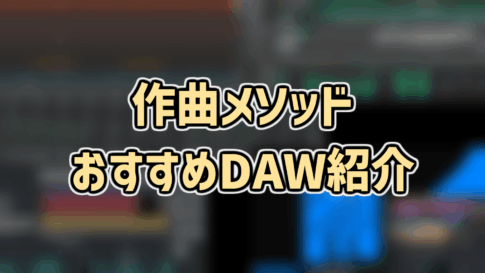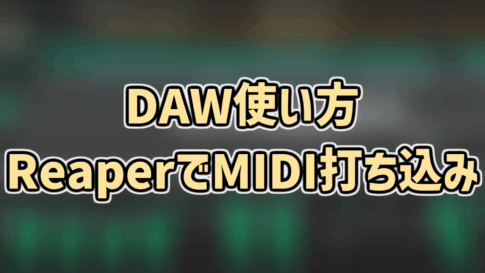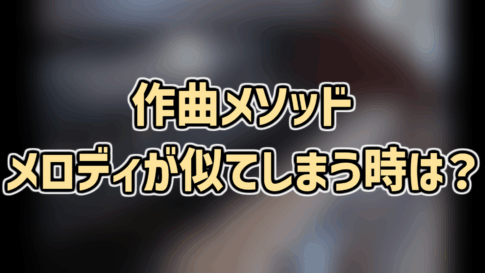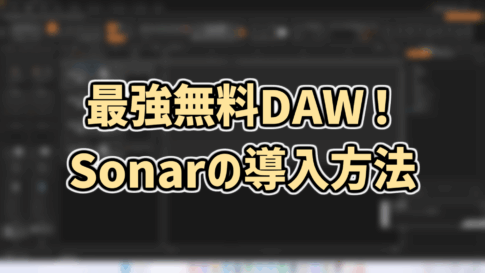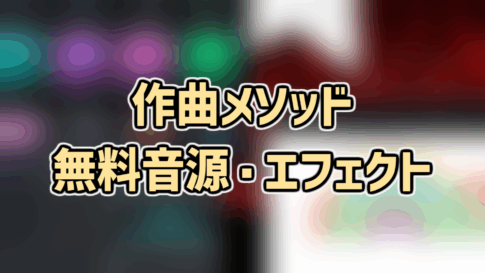皆さんごきげんよう。IWOLIです。
今回から作曲解説という事で、
ゼロから曲を生み出す方法について一つずつ解説していきます!
色んな曲を聴いて「自分もこんなの作ってみたい!」と思ったものの、
必要な知識や準備が多過ぎてどこから手を付けたら良いのか…と、尻込みしたり諦めてしまった経験、ありませんか?
そんな皆さんのために今回からは、
この作曲メソッドシリーズを通して作曲のイロハをお教えします!
今回は作曲の基礎として、
そもそも作曲とは何をするのか、その大まかな手順・流れを説明します。
それでは行きましょう!
Contents
手順:作曲ってどうやるの?
まずは作曲全体の簡単な流れを順番に解説します。
ここを踏まえずに曲を作ろうとしても、
「何から手を付ければいいか分からない」
「どこがダメで変に聴こえるのか分からない」
という事になりかねません。
ざっくりと押さえていきましょう。
僕は作曲とは基本的に、こんな感じに作っていくと思っています。
- テーマ
- 作曲
- 作詞
- 編曲
- ミキシング
- マスタリング
意外と多いと思われたでしょうか?
実際多くの方が認知されているのは、
作詞作曲や作編曲という言葉ではないかと思います。
実際にこれは特に重要な要素ではありますが、
より簡単でスムーズに、計画的に、よりよい曲を作るためにはそれ以外の工程も大切です。
順番に解説していきますね!
テーマ:何故この曲を作るのか?
1番最初は「テーマ」です。
多くの場合は最初に「作詞」が書かれて居たりするかな?と思います。「作詞作曲」と言うくらいですからね。
ですが僕はこのテーマ決めこそが作曲において最も大切な工程だと思っています。
テーマとは即ちどんな曲であるかという答えそのものです。
言い換えると正に「何故この曲を生み出したか」ということですね。
意外とすっぽ抜ける事もあるかな?とは思うのですが、
ここが無いと、特に歌ものでは苦労すると思います。
何でこの歌を作っているかが曖昧だと、
次にどう展開すればいいか、結局何が言いたいのかが不透明になってしまいます。
歌の無いインスト曲ならそこまで重く考える必要はないかもしれませんが、
それでも、この後の作編曲においてテーマが定まっているか否かで、
次何をすればいいかに対する回答スピードがかなり変わると思います。
過去にこういった手詰まり感を経験したことがある方は特に、
是非このテーマを詳細にしてみてください。
作曲:どんなメロディ・コード?
2番目は遂に作曲、これは曲のメロディやコードを考える工程です。
「先に作詞じゃないの?」と思われるかもしれませんが、
少なくとも特に平成~令和にかけての日本の傾向としては、
作詞より作曲を先にやっておいた方がスムーズになると考えています。
所謂「メロ先」というものに近いですね。
過去には歌詞を書いておき、言うならばそれを
伴奏に合わせて語り口調で淡々と綴るような曲もありましたが、
今のメジャーシーンは専ら、キャッチーなメロディに合わせた、
時として文法的には未完成だったり変な歌詞を綴るものが席巻していると思います。
落ち着いて思いを語るようなバラードでもない限り、
先に曲を作っておいた方が「それっぽい曲」になりやすいでしょう。
作詞:どんな言葉で何を伝えるか?
3番目にしてやっと作詞です。
これはもちろん、目指すのが歌ものだった時であって、
インスト曲が作りたいならここは飛ばします。
また作詞とは、ある程度の上手く行く方法こそあれど、
結局は夥しい数の単語から相応しいものを思いつき選び抜く途方も無い作業です。
かなり脈略の無い言葉の羅列が大バズりする事もある様な世の中なので、
最も上手く行く方法が未解明な工程と言えるでしょう。
編曲:どんな楽器?どんな曲調?
4番目では編曲に入ります。
作曲との大きな違いは、編曲はまさに肉付けと言えることでしょうか。
作曲ではメロディとコード、要は五線譜に書き起こすような曲の基礎情報を決めました。
編曲はその基礎情報に当たるメロディやコードを、
何の楽器でどのように奏でるか、
或いはリズムや効果音などを用いて、
最初に決めた目標たるテーマをいかに表現するかを決める工程です。
この編曲と作曲は完全に切り分けられない時もあります。
例えば「ギターではこの音は鳴らせないからコードの構成音を変える」といった感じで作曲に戻る事もあります。
作詞・作曲でも曲のモチーフやイメージが大きく左右されますが、
それに勝るとも劣らないほど編曲は大切な項目です。
ミキシング:各パートのバランス
5番目のミキシングは聞きなれない人も多いかもしれません。
或いは歌ってみたに明るければ、ボーカルのミックスについては認知されているでしょうか。
このミキシングとは編曲で決定した楽器や音の構成の、
各パートをバランス取りする工程です。
例えば極端な話、
ボーカル・ギター・ベース・ドラムが居るバンドなのに、
楽器の音は聴こえるけどボーカルの声が聴きとれなくて、
何を歌っているのか分からないという状態は残念ですよね?
ライブなんかではその場でバランスが取れなかったりという事もあるわけでしょうが…(にわかなのに偉そうにすみません)
こういった音量バランスに限らず、様々な面から目指すべきバランスに整える工程がこのミキシングです。
ボーカルとそれ以外でのバランスに限定したものと言えますね。
これだけでも何気に奥が深かったりします。
マスタリング:どんな環境でも聴ける様に
最後6番目はマスタリング、これはちょっとややこしいです。
そもそも本来のマスタリングとは、CDをプレスで量産して流通出来るようにするための、
マスターCDを作ることを指していたようで、
それまでの部分はプリマスタリングと言っていたようなのですが、
僕が見た所では現在ではマスタリングがそのままかつてのプリマスタリングを意味している事も多そうです。
この工程は超平たく言うと、
どんな環境でも聴ける音源にする、と言ったところでしょうか。
正に、ミキシングで出来上がっていた音源の最終調整ですね。
とんでもなく繊細なので実際には一番難しいと言っても過言ではないかもしれません。
本気でやるならむしろエンジニアに依頼すべき工程でしょう。
お便利なツールでより簡単手軽に済ませるパターンも多いと思われます。
\Ozoneドーン/
まとめ
以上、簡単な作曲の手順解説でした。
少し数が多くて大変そうに見えるでしょうか?
ですがいきなり最初から全てを網羅できる必要はありません。
特に最初の作品なんて編曲以降ぐっちゃぐちゃ(何なら最初から変)みたいなことになっちゃいますよね…
僕も最初はミキシングのMの字も認知の外でした。
また作曲ではなくリミックスをすることで、
最初の作詞作曲をスルーするという手もありますね(ボソッ。
・・・まあそれはそれとして、
まずは複数ある工程の中で特にやってみたいと思う部分から始めるくらいでもいいと思います。
それをしていて、「なんか変だな?」とか「もっと違う感じにしたい!」と思えてきた頃に、
別の工程を詰めてみましょう。
必要に迫られた時が一番学びがありますからね。
これから少しずつ勉強していきましょう!
それではオヤカマッサン~