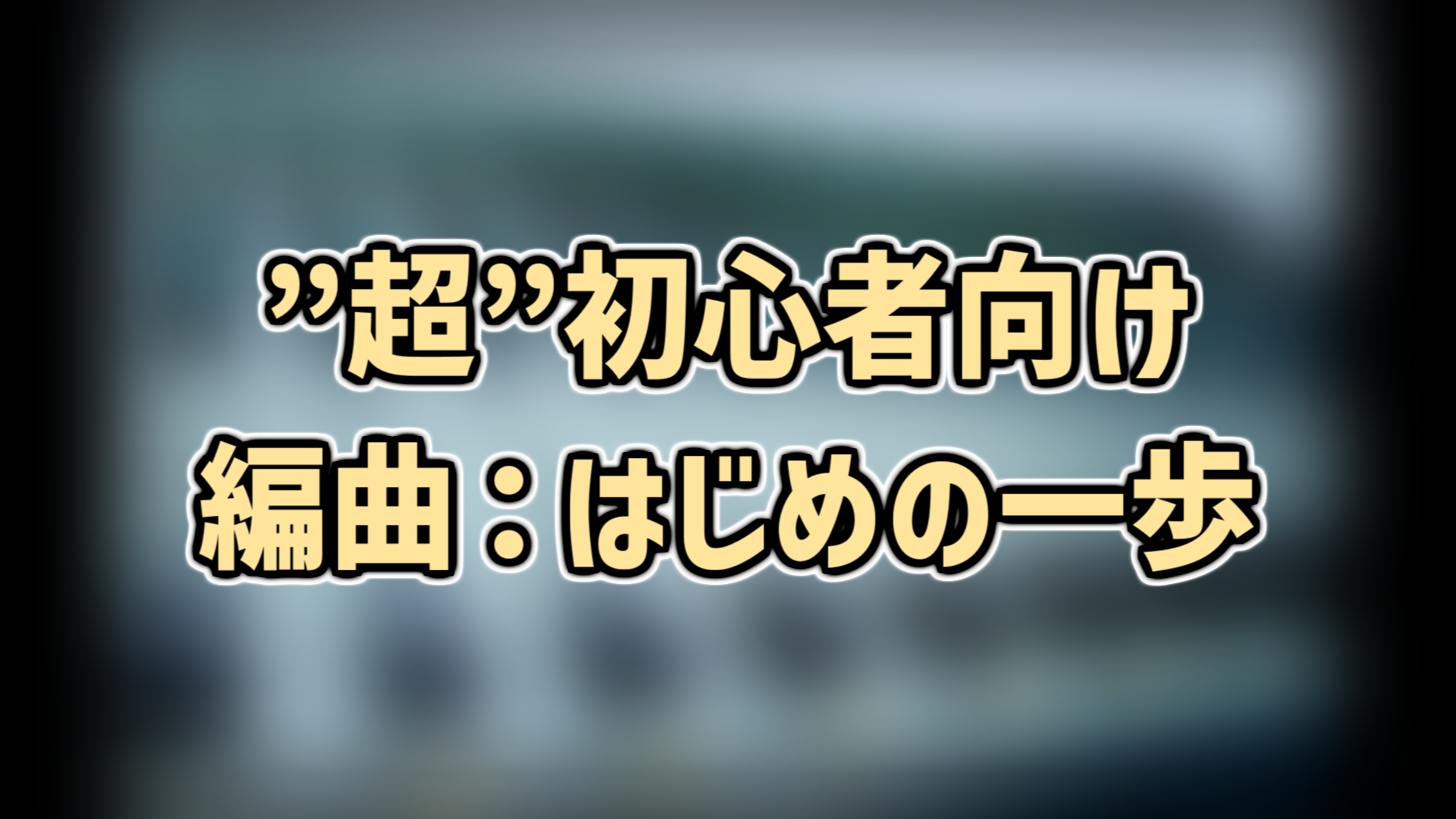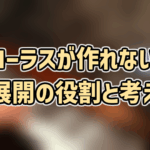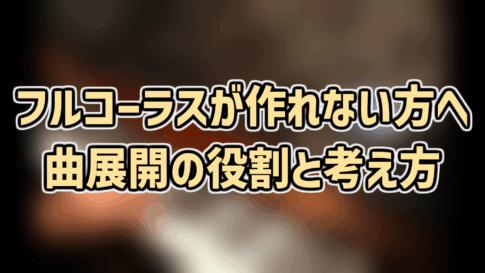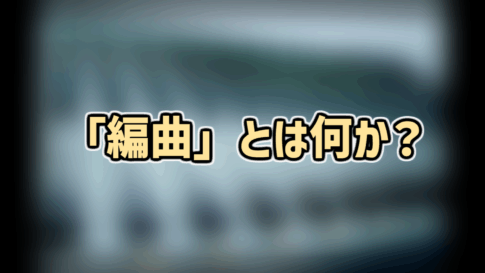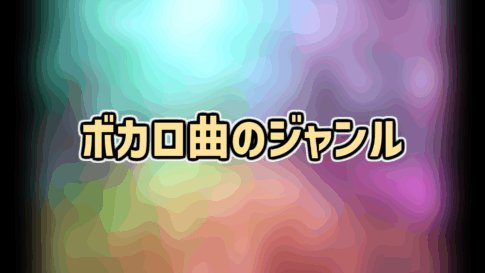皆さんごきげんよう、IWOLIです。
今回は、編曲をやった事が無い!分からない!という方のために、
これだけあればそれっぽくなる編曲の始め方を解説します。
「作曲をやってみたいけど、ピアノで鳴らしてるだけで滅茶苦茶ショボい…」
「そもそも耳コピしかしてないし、メロディしか無いから地味すぎ!」
こんな感じで悩んでいる方は必見ですよ!
今回の記事を読んで実践してみれば、色んな楽器をどう活かせばいいか、
インストを賑やかに出来るかが分かる様になりますので、
是非最後までご覧ください!
Contents
編曲の始まり:必要な音の役割を洗い出す
まずは編曲について考えるために必要な基礎知識について!
編曲とは、作られた曲を何を使って、どのように演奏するかを決めて、
作品を演出することです。
ですがそれ以前にどんなパートを演奏するのかが分かっていないと、
必要な楽器の種類や数が分かりません。
先に答えを言ってしまいますが、
編曲で考えるパート・役割は主に以下の4つに分けられるでしょう。
- メロディ(単音)
- コード(和音)
- ベース(土台・低音)
- リズム(打楽器)
これらの役割に適切に楽器を割り振り演奏させれば、どんどん楽曲を魅力的に彩ることができます!
またこれらの役割はさらに細分化していくので、順番に解説していきますね!
ここだけ見ると、4種類の役割が必須条件に見えてしまいますが、
実は一部が存在せずとも成立する音楽はあります。
こちらは最後に紹介しますね!
メロディ
まず最も目立つメロディから。メロディラインなんて言ったりもしますね。
言わずと知れた花形かつ主役です。
特徴は単一の音でピッチ(音の高さ)やリズムがある(動きがある)ということ。
とても分かりやすい存在ですが、幾つか種類があるので解説します。
リード
リード(Lead)、つまり曲を先導する存在です。
メロディとリードが同義として扱われているケースも多いですね。
歌もののボーカルもこれにあたることが多いでしょう。
詳細は後述!
ハモリ
ハモりとは英語の”harmony”に由来し、メインの音と異なるピッチでメロディを奏でることです。
音の高さ、ピッチは違いますがリズムが一致していて、一緒に鳴るイメージですね。
リードと合わせてコードを形成しているとも解釈できますが、
ピッチの動きが大きく、空気感というよりメロディに雰囲気を足すイメージに近いでしょうか。
考えることが多くなるため初心者には少し難しいですが、出来るとカッコイイ!
オブリガート
オブリガートとは、これまでとは一風変わり、
メインのリードたちとは全く別のメロディを奏でることを差します。
カウンターメロディと呼ばれることもありますね。
ハモリのような分厚さではなく、メインの音と掛け合うような存在になり、
曲に面白さを加えられます。
こちらも簡単ではないでしょうが、ハモリよりはやりやすいかもしれません。
コード
2つ目がコードです。
「作曲はメロディとコードを作ること」というくらいですから、
コードとして何をどう鳴らすかはとても大切です。
このコードという役割の中でも、鳴らし方で幾つかに分けられます。
パッド
まず最も基本的な奏で方がこちら。
パッドは詰め物とか埋める物という意味で、その名の通り音の隙間を埋める役割を持ちます。
パッドという呼び方はシンセや電子音楽的ですが、同じ考え方は生楽器にも言えるでしょう。
サステイン(持続音)とも言えるでしょうか。
特徴は長く鳴り続ける音で、コードが変わるまで同じ音を鳴らし続けることです。
ずっと音が鳴っている状態に出来て雰囲気的な寂しさを緩和するのに役立ちますが、
ずっと鳴っているため間延びしたり退屈になってしまう恐れもあります。
そういった問題を解決できる一例が次です!
バッキング
バッキング(backing)とは名の通り後ろにいる存在で、伴奏と訳されますが、
パッド・サステインとの違いとしてリズムがあるというのが大きいですね。
ギターのバッキングがイメージしやすいでしょうか。
パッド的なギターの場合「ジャ~~~~ン…」という感じになりますが、
バッキングの場合は「ジャカジャカジャカジャカ」と何度も鳴らします。
リズムがあるためノリがよく、特にシンコペーションなどを強調すれば、
小気味よく疾走感のある楽曲を演出できます。
アルペジオ・シーケンス
更にアルペジオというテクニックがあります。日本語では分散和音と言われます。
これは和音の構成音、例えばCメジャーなら「ド・ミ・ソ」の3つを、
同時ではなく順番に鳴らしていく奏法のことです。
ギターで6弦から1弦にかけて「ジャラララ~~ン」と鳴らしているのが分かりやすいでしょうか?
他にもピアノで低音から高音まで「ポロロン」と鳴らしたり、
シンセのアルペジエイターという機能を使い「ピポパポ」鳴らすこともあります。
パッドと違ってこれもリズムがあるため疾走感が出やすく、
またバッキングとの違いとして和音を一斉に鳴らさないのでより軽快さや細かさが出せます。
曲中では目立ちにくいことも多いですが、微かに聴こえて雰囲気を付け足していることが多いですね。
たまに、アルペジオと呼ばれているけど単音しか鳴らしていない(ずっと「ド」など)
というケースがあります。
本来ならアルペジオは「分散”和音”」なので誤りのはずですが、特にシンセなどで、
1つの音のオクターブ違いを飛び回って鳴らしている音をアルペジオと呼ぶことは意外とあります。
厳密にいうならこれは「シーケンス」と呼ぶのが正しいのかなと思っています。
ベース
次はベースです。重低音の土台ですね。
いよいよ、作曲の時点では決まっていない部分に来ましたが、
ベースに関してはあまり難しく考えなくていいと思います。
何故ならベースはコードの構成音、基本的には最低音を奏でるパートだからです。
そしてベースは他のパートに比べて演奏法もそこまで多くありません。
常に低音で曲の土台を担うため、あまり大きく変化をつけるということがしにくいんですね。
最初は特に基本的なベースの形と言える、裏打ちとオクターブベースくらいで問題ないでしょう。
- 裏打ちベース:裏打ち(1,2,3,4,というリズムのそれぞれの間)に鳴るベース
- オクターブベース:八分音符でオクターブ下と上を行き来するベース
裏打ちベース
オクターブベース
どんなベースでも共通して気を付けるべきはオクターブだと思います。
高過ぎても土台という役目を果たせず、低過ぎると聴こえません。
メロディ・コードだけでなく、ベースをちゃんと配置してあげると楽曲に締まりが出ます!
本旨と逸れるので割愛します。
リズム
最後にリズム楽器について解説します。
基本的にはドラムなどのパーカッション・打楽器があたりますね。
木琴鉄琴も打楽器ですがリズムのための楽器というわけではないので…
またリズムとは言えないこともありますが、曲の要所要所に差し込む効果音もここに含められるかもしれません。
有り金溶けそう
肝心の編曲についてですが、これまでのパートが奏法にフォーカスしたのに対して、
ドラム・パーカッションは楽器、何を鳴らすかでの役割分担の方が重要だと思います。
確かに同じ楽器でもどんなリズムかで雰囲気はガラッと変わりますが、
それ以上に楽器が違えば全く異なる役割になるためです。
ここではその中でも特に重要な役割を紹介!
キック
ドラムで最も重要な楽器はほぼキックで確定でしょう。
ベースが土台として大事だったように、ドラムもキックを土台として、
曲全体のリズムを支える役割を果たします。
生楽器でも多くのジャンルがそうですし、電子音楽では更に重要な存在になりますね。
スネア
2番目に重要なドラムがスネア、「ッタァーン!」と気持ちいい音を奏でます。
力強く、高い音が鳴る一方でシンバルほどは響かないため、
キックとの掛け合いでメインのリズムを完全な物にします。
シンバル
3つ目にシンバルを挙げましたが、
シンバルはその中でも全く異なる役割を持つものが幾つかあります。
今回はその中で3種類を紹介しますね。
クラッシュシンバル
一番目立つと言っていいのがこのクラッシュシンバルでしょう。
「バシャーン!」とド派手な音を奏でます。
とても目立つため、イントロやサビの始まりなどで
「こっから次のパート始まりまっせー!」というアピールが曲の説得力に繋がります。
逆に言うとかなり主張の強い音なので、ここぞという場面以外では連発厳禁!
ライドシンバル
さっき補足したライドシンバルは、
見た目こそクラッシュシンバルに似ていますが、機能は全く別物です。
クラッシュの様な強い音は鳴らず、「キンキン」という高く小気味よい音を奏でます。
程よい力強さもあるため、サビなどで盛り上げる時に連発するのはこちらになりがちです。
またジャズではこのライドシンバルを軸にドラムを組み立てるようです。
ハイハットシンバル
ハイハットシンバルは見た目では一番異色のシンバルと言えます。
ドラムセットでは左端にいる、パタパタ開閉する奴ですね。
ペダルを踏んでこれを閉じれば、「チッチッ」という小さい音が鳴り、
開けば「チーッ」とか「シャーン」というライドシンバルに近い大き目の音になります。
不思議な存在ですが、実際の曲ではむしろ一番仕事が多い子でもあります。
一つで複数の役割を果たせる上にそこまで主張が強くはないので、
「小さ目の音で疾走感を出す」とか、「キック・スネアを休ませた静かな中でリズムを刻む」といった時にも重宝します。
その他の打楽器・効果音
他にもドラムスに含まれる楽器や、
ドラム以外の打楽器、電子音楽ならではの効果音など、
挙げ出したらキリがないくらいの色んな音がありますが、
それらは全て「その音が持つ特性が演出する雰囲気」を活かすために使われます。
最初は上記の5つを使ってみて、更にステップアップしたい時に色んな音を使ってみましょう!
一部が欠けた音楽
最後に冒頭に言った4つの役割の内、一部が欠けた音楽を幾つか紹介します。
4つの役割、メロディ・コード・ベース・リズムが揃っていなくても成立する例ですね。
メロディとコードしかない音楽
まずはメロディ・コードの二つだけで完結した音楽です。
これは比較的イメージしやすいと思います。
なんたってこういった動画がまさにそれですから!
むしろネットに生きてまらしぃ様を知らない人が居るだろうか?(反語)
現状一番再生されているのがこちらの様ですが、
かなりの数の曲を一人の圧倒的なピアノ演奏で表現されていますよね。
こちらは右手のメロディと左手のコードの二つだけで構成されていますが、
解釈によっては特に左手がある程度ベースやリズムも兼任する事で、
寂しさや物足りなさは一切ない、むしろゴージャスにさえ感じる演奏ですよね!
ベースとリズムだけで出来た音楽
一方でその逆、ベースとリズムしか無いような音楽も実はあります。
え?そんなの何を聴けば良いんだって?
じゃあ…これはどうかな?
ボーカルがあるためある意味メロディと言えばメロディと言える所もありますが、
大部分がピッチ感をそぎ落としたラップで構成されています。
ラップ、即ちリズム重視の歌ということになりますね。
更にオケの方も大部分がリズム楽器とベースであり、
カリンバやピアノっぽい音こそあれ全体的にかなりストイックな印象です。
この曲は”Jersey club”と呼ばれるジャンルなのですが、
実際にはもっとメロディ・コード感を削ぎ落したストイックな物もあります。
メロディがある所もありますが、リズムとベースで踊らせる感じが強いですね。
え?「やっぱりどこかにメロディが入ってるじゃないか」って?
Current Value「なんか言った?」
Current Valueなどが作るこういったスタイルは“NeuroFunk”と呼ばれます。
電子音楽、EDMの世界ではこういった、ベースはメロディ、ベースが主人公と言わんばかりのスタイルも沢山あります。
リズムしかない音楽
さて既に相当ストイックなのが出てきましたが、
世の中にはもっとストイックな音楽も有ります…
僕が知っている中で過去一番ストイックだと思ったのがこちら。
なんと、音程を奏でる楽器はゼロ!(厳密には打楽器にもピッチはあるのですが)
曲全体がこんな感じでメロディ・コード・ベース無しなのにクセになるんですよね…
まぁ、日本にもそういう文化がありますからね。
実は和太鼓大好きだったりします。(隙自語)
まとめ
ということで今回は、編曲の基礎という事で、
超初心者向けの編曲講座でした。
「編曲の事まったくわかんない!」という方は、
この辺りを是非参考にしてみてくださいね!
今後はより踏み込んだ編曲の手段や、楽器ごとの打ち込み方
ジャンルごとのアプローチについても解説予定です!
お楽しみに~オヤカマッサン!