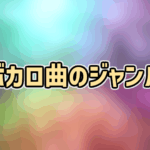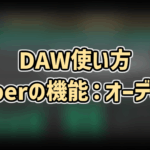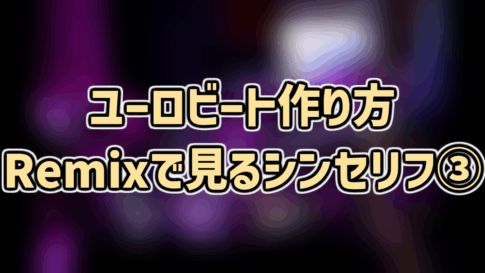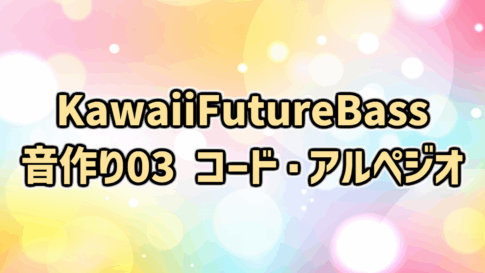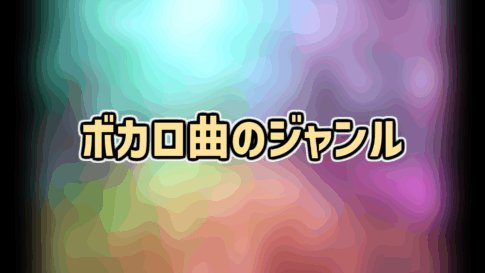皆さんごきげんよう、IWOLIです。
今回は電子音楽のジャンルに関する前提として、
そもそも電子音楽やEDMが何を指すのかについて解説します。
巷でよくEDMとかって言ったりしますが、
具体的にどんな音楽を指しているのか理解があやふやな方は多いのではないでしょうか?
今回はそこについて解説しつつ、電子音楽の大まかな分類についても紹介します!
人によって理解や解釈の幅がある事でもあります。
あくまでいち個人の解釈なので、鵜呑みにし過ぎず「より知るためのきっかけ」にしていただければ!
あと単純に知識不足…勉強しないとですね…
そもそもEDMとか電子音楽、テクノ・クラブミュージックって何が違う?
では早速、そもそも論の話をしましょう。
EDMって何なんだ~??
巷でよく聞くようになったこの単語は、
”Electronic Dance Music”(エレクトロニック ダンス ミュージック)の略称で、
直訳すれば「電子的な踊るための音楽」となります。
日本人にとっては馴染みがない人も多そうですが、クラブハウスなどで大勢の観客が、
暗い部屋の中、重低音とギラギラな照明に包まれ踊っているのは見たことがありますでしょうか?
TeddyLoid氏「アメリカのハロウィンも「唱」でブチ上げました」
こういう場所で、観客をガンガンに踊らせる曲の総称がEDMと言えます。
EDM・クラブミュージック・テクノ・電子音楽って違いあるの?
さてそうなると次に疑問になるのが類語だと思います。
EDMという言葉の他に、「電子音楽」とか「テクノ」という言葉もあり、
むしろ後者の方が馴染みがある方も多いかもしれません。
これらは似ているどころか、例によってこちらも定義は結構曖昧なものですが、
今回は言葉の発祥などから「だいたいこういう時に使われる」という大まかなイメージについてお話しできればと思います。
EDM
EDMという言葉は前述の通り、「電子的な踊れる曲」を指して使われますが、
実は言葉の発祥は2000年代後半から2010年代と割と新しめです。
起源となったジャンルこそ古く、それらをEDMとくくる事も不可能ではないですが、
単語として「EDM」が生まれ認知されていったのが新しめということですね。
また単語の生まれや使われるシーンの傾向からか、
- 狭義:特に現在主流のジャンルのみを指す場合
- 広義:電子的な曲全部を指す場合
の2パターンに分かれる印象があります。
クラブミュージック
クラブミュージックという言葉もあります。
こちらはより広義に使われている印象がありますが、現代はEDMを表すことも多いでしょうか。
なんたってクラブでガンガン流される曲が「電子的な踊れる曲」ですからw
ですがクラブミュージックという言葉を、
今主流では無い、昔からのジャンルに使ってもEDMほど違和感はないでしょう。
個人的にはこの「クラブミュージック」は特に便利な印象があります。
テクノ
日本で聞き馴染みあるという方が比較的多そうなのがこの「テクノ」ではないかと思います。
何せ音楽ジャンルを表す「テクノ」という言葉の発祥は古く、
1970年代~1980年代辺りに使われだしたようです。(諸説あり)
或いは日本だと「テクノポップ」の方がより浸透していそうですね。
ただこのテクノが厄介で、考え方によって幅が極端に変わります。
- 狭義:デトロイトテクノ(後述)に端を発する、ストイックな4つ打ち
- 広義:電子音楽
ふざけんな、って話ですね。
狭義のテクノともかなり違ったポップで親しみやすいジャンルです。わけわかめ
これは万国共通なのか、日本独特なのかは僕も分かりません。
テクノが流行った当時、電子音楽と意味がくっついてしまったのかもしれません。
一見便利ですが、どっちを表すのか分からないので僕は狭義でしか使いません。
広義を表すなら、次の「電子音楽」で解決しますから。
電子音楽
「電子音楽」という言葉の歴史は更に古いです。まあ漢語繋げただけですし。
何ならこれは「電子的に音を発する」という事が実現した時点で生まれたと言っても過言ではないでしょう。
その試みは19世紀終わり~20世紀には始まっていたようで、歴史・範囲ともに最も広いジャンル名と言えますね。
そして好都合にも別の意味合いも特になく、ひたすらだだっ広い意味を持ちます。
厳密にはかなり古いジャンルも指しますが、それらと分ける必要もあまりないでしょうから、かなり実用的な単語だと思います。
各用語のまとめ
ここで一旦セーブポイントとしておきましょう。
出てきた4つの単語を、(一部狭義広義含め)広さ順に並べると、
電子音楽≧広義テクノ>クラブミュージック≧広義EDM>狭義EDM>狭義テクノ
という感じになると思います。
電子音楽・広義のテクノに比べると「現代的な電子音楽」辺りに絞られる印象があります。
もちろん人によって解釈などの揺れはあると思いますので、
実用時は擦り合わせが必須なんですけどね!
EDM・電子音楽を区別する時の基準
簡単にEDMなどの、電子音楽を広く指す言葉の意味はなんとなく分かって来たかと思いますが、
ハウスとかトランスとかを知っている方は、
今度はそれらのジャンルがどう分けられているのか?というのが気になると思います。
お次はそんな、数ある電子音楽を区別する基準について解説します。
基本は「BPM」と「リズム」
先に結論を言うと、電子音楽において大枠のジャンル区別はほとんどが、
- BPM
- リズム
の二つの要素を基本に区別されます。
理由は電子音楽・クラブミュージックが基本的に、
クラブハウスでDJが複数の曲を繋げ、延々と流し続ける事を前提としているためです。
曲を繋げる上では、リズムはともかくBPMが変わり過ぎると滑らかに繋ぐのが難しくなるため、
「このジャンルと言えばこれくらいのBPM(テンポ)!」という情報が重視されます。
一方のリズムも大きく変わってしまうと、それまでの流れが意図せず著しく変わったり、
リスナー的にも踊り方が変わり過ぎる可能性もありますね。
と言ってもBPMが同じくらいでリズムが変わるのはまだ許容範囲が広めだと思っていす。
むしろ意図的にリズムが異なる曲を挟むDJなんかもいらっしゃいますね。
(Drum’n’BassとHardcoreなど)
サブジャンルではその他の要素も変わってくる
そしてテンポとリズムで大まかに「ハウス」などにジャンル分けされた後で、
その中で更にスタイル・サウンドの違いで区別されていきます。
これらはサブジャンルと呼ばれ、ここで曲の雰囲気も含めた具体的な特徴が定まります。
多くの方はジャンル分けと言えばこういった曲調や雰囲気で分けるイメージを持たれているかもしれませんが、
電子音楽ではそれ以上に重要な要素があるということですね。
ちなみに、さっきのジャンル(個人的には親ジャンルと呼んでいます)でテンポとリズム、
サブジャンルで曲調が決まってくるとは言いましたが、やはり例外はつきものです。
例えば、BPMでは区別しきれない親ジャンルや、
サブジャンルによってはBPMがぶっ飛んでいくようなケースもたまにあります。
色んな電子音楽を見てみよう!
さて、電子音楽がどのようにして区別されるか分かった所で、
代表的な電子音楽・クラブミュージックを幾つかご紹介します!
ここが一番楽しい所です!(聞いてない)
今回はあくまでざっくりとした分け方でのみ解説しますが、
大まかな「BPMとリズムでの差」を感じていただけると嬉しいです。
House:ハウス
現代の電子音楽を語る上でHouseは絶対に欠かせません。
何と言っても今のメインストリーム(=主流)を搔っ攫い、
EDMという単語を流行させたのは間違いなくHouseの強さあってのことだからです。
特徴は主に以下です。
- BPM:120~128辺り
- リズム:4つ打ち
大体軽い運動をしている人の心拍数くらいのスピードで、
とにかく単純に「ドン、ドン、ドン、ドン」というリズムを繰り返し、
その上で曲が展開していく、とても親しみやすいジャンルです。
やはりこの親しみやすさが万人にウケた理由と言っても過言ではないでしょう。
例えばこんな感じ。
再生数が圧倒的過ぎる…ホントにカッコいい。(でも車燃やさないでー!><)
発祥はシカゴ、ウェアハウスというゲイクラブで生まれたらしく、
当時の特にソウルフルとされるサウンドのHouseは、Chicago House(シカゴ・ハウス)と呼ばれています。
今特に人気なのは上記のAnimalsなどのBigRoom House(ビッグルーム・ハウス)の他、
それを内包するElectro House(エレクトロ・ハウス)、
Progressive House(プログレッシブハウス)系などでしょうか。
Progressive Houseはこれまた結構ややこしかったりするんですがね…
Techno:テクノ
ここで言うTechnoは先ほど説明した内の狭義の方です。まあ今更広義いう訳ないし
いきなりなんですが、こちらはリズムテンポともにHouseと酷似しています。
- BPM:120~150(曲によってはそれ以上)
- リズム:4つ打ち
そもそもTechnoが、Chicago Houseと近い時期に生まれ、
影響を受けつつ進化したというのが大きいと思います。
その中で異なる点は、Technoはより機械的・無機質さが強調される事。
発祥はデトロイトで、そこで生まれたスタイルはDetroit Techno(デトロイト・テクノ)と呼ばれます。
シンセサイザー・効果音がより多用されているのが特徴ですが、
先ほどの通りテンポ・リズムがHouseとかなり重なっているので分けるのは結構難しい所です…。
僕も自信はあまりないですが、「これはTechnoっしょ」というのを貼っておきます。
確証が全然なく、調べが足りないだけかもしれませんが、
サブジャンル派生を数えるとHouseや後述のTranceなどに比べて、
Technoのサブジャンルは多くない様に見受けられます。
ストイックでハード寄りでこそTechnoという事なのでしょうか…
個人的にはTechnoよりも、後述のHardcore Technoの方がよっぽどサブジャンルが多いなと思います。
Trance:トランス
Tranceは先述のTechnoやHouseから派生した、僅かに若いジャンルです。
主な特徴はこんな感じ。
- BPM:130~150くらい
- リズム:4つ打ち
リズムは変わらず4つ打ちですが最大の特徴が、ちょっと速いことです。
それでもTechnoと近い所がありますが、大きな特徴はやはり曲調。
Technoに比べキック・ベースといった低音も、中高域のシンセも
いずれもが強くハッキリしていて重厚感があると言えるでしょうか。
包み込むような音であったり、意識を持っていくようなサウンドが、
リスナーに陶酔感を与える事から”Trance”と呼ばれるようになりました。
こっちだと、「超えて」とか「通って」といった接頭語になってしまいます。
音数も多く分かりやすいことが多いため、House・Technoとは区別されてこちらも人気があります。
例として適切かは分かりませんが…この曲は凄く好きです。
ユーロビートの解説で「ユーロビートではない曲」としてちょっと紹介した曲。
ホンマ綺麗。
またTranceの特徴が、サブジャンル派生があり過ぎる事だと思います。
細かく分けだすとちょっと気が触れそうなので、僕は
- Euro系:高音重視
- Psychedelic系:低音重視
- Hard系:キック重視
という3種類で分ける考え方を推しています。
さっきの”The Rampage”はEuroとHardの間って感じがしますけどね。(やっぱり例として不適じゃないか)
Hiphop:ヒップホップ
正確には「ヒップホップ」という言葉は、音楽だけでなく、
ニューヨークから始まった、ブレイクダンスやグラフィティなども全てひっくるめた文化を指す様です。
と言っても、音楽が余程メジャーなのか「ヒップホップ」と言っただけで、
音楽、即ち「ヒップホップ・ミュージック」(Hiphop Music)を指すことも多いですね。
1970年代に生まれ、未だに”Hiphop”と呼ばれ親しまれる歴史ある電子音楽ですが、
このHiphop Musicの電子音楽的な特徴は何と言っても、
基本的に4つ打ちじゃないという事。ここにきて遂に来ましたね。
Hiphopではブレイクビーツ”Breakbeats”というテクニックが多用されます。
このリズムがFunkに由来するちょっと複雑でお洒落なリズムで、
典型的なHiphopを特徴付けています。
そしてこのHiphopがまた一大ジャンルでして、そこから数多のスタイルへ派生・影響していきます。
凄く申し訳ないんですが、残念ながら僕はこのHiphopには極端に疎いです…
間違いや誤解を招く表現があったらごめんなさい。
BassMusic:ベースミュージック
Hiphopから派生していき、これまたデカいジャンルになったモノたちをまとめた、
「ベースミュージック」”BassMusic”と呼ばれている一大グループもあります。
全体に共通する特徴は、
- 名の通り、原則としてベースが主役である
- 4つ打ちじゃない(Hiphop由来)
が挙げられるでしょう。
一方でそれ以外の特徴はBassMusicとして解説するのは困難でしょう。
何故なら、あくまでHiphopから派生したというだけでそのスタイルは多岐にわたるためです。
ここに来た方にも、「ダブステップ」”Dub Step”や、「ドラムンベース」”Drum’n’Bass”という事がを聞いたことがある方もいらっしゃるのでは?
”Drum’n’Bass”は”Hiphop”派生って訳では無いけど…
これらはそれぞれ独自に発展したため、メインのリズムやテンポなどは最早別物。
こうして「全然違う特徴を持つ物たちだけど、まとめて”BassMusic”と呼べる」という事でこのように紹介しました。
気になるという方のために、”BassMusic”の中の代表例を幾つか挙げていきます。
- Drum’n’Bass
- Dub Step
- Trap
- FutureBass
etc…
挙げ出せば幾らでも出せるのでこのくらいで…
Hardcore Techno:ハードコアテクノ
「またTechno?」と思うかもしれませんが、最早別物と言った方が良いと思っています。
理由は何よりそのテンポ。Hardcore Technoの主な特徴を見てみましょう。
- ほぼ4つ打ち(稀に例外のサブジャンル有り)
- BPM:165~
幾らでも
そう、これまででダントツに速いです。(サラっと流したDrum’n’Bassも速いですが)
これは元々はTechnoだったはずのものを、加速させ過激にしたことで生まれました。
Mescalinum United – We Have Arrived
最初の”Hardcore Techno”(ガバ”Gabba”)とされる曲がこちら。
これだとまだ「うるっせぇTechno」という感じでしたが、
ここからこのジャンルは高速な4つ打ちとして定義され、
逆にそれ以外の要素が大体何でもいいという「この上なく自由奔放な世界」になりました。
元は「Technoが激しくて速くなったやつ」として”Hardcore Techno”と名付けられましたが、
今では略されて多くの場合”Hardcore”とだけで呼ばれている印象です。
”Hardcore”という言葉は元々、”core”が「中核」を表すことから、
本来は「原理主義」とか「中核の過激派」みたいな意味だったようですが、
パンクロック”Punk Rock”の原理主義、”Hardcore Punk”が速くて激しかったため、
その内”Hardcore”という言葉が、「速くて激しい」という意味に変わったようです。
という事は”Hardcore”だけだと色んな接尾語が有り得てしまうので、
電子音楽の話をしている前提でない時は”Hardcore Techno”と呼ぶ方が親切かなというのが持論です。
詳しくはこちらで!
色々な記事を出しててお察しかもしれませんが。
と言ってもまだまだ序の口、電子音楽の世界は深いよ…深淵だよ…
まとめ
という事で今回は音楽ジャンルの内、電子系を知る上での基礎知識について解説しました。
僕もまだまだ勉強不足で恐る恐るですが、大まかな基準を把握するだけでも、
これから聴く音楽の聴こえ方が変わってきて楽しいですよ!
という事で今回はここまで。良かったらより細かいジャンル解説も見ていってくださいな。
ではでは、オヤカマッサン~