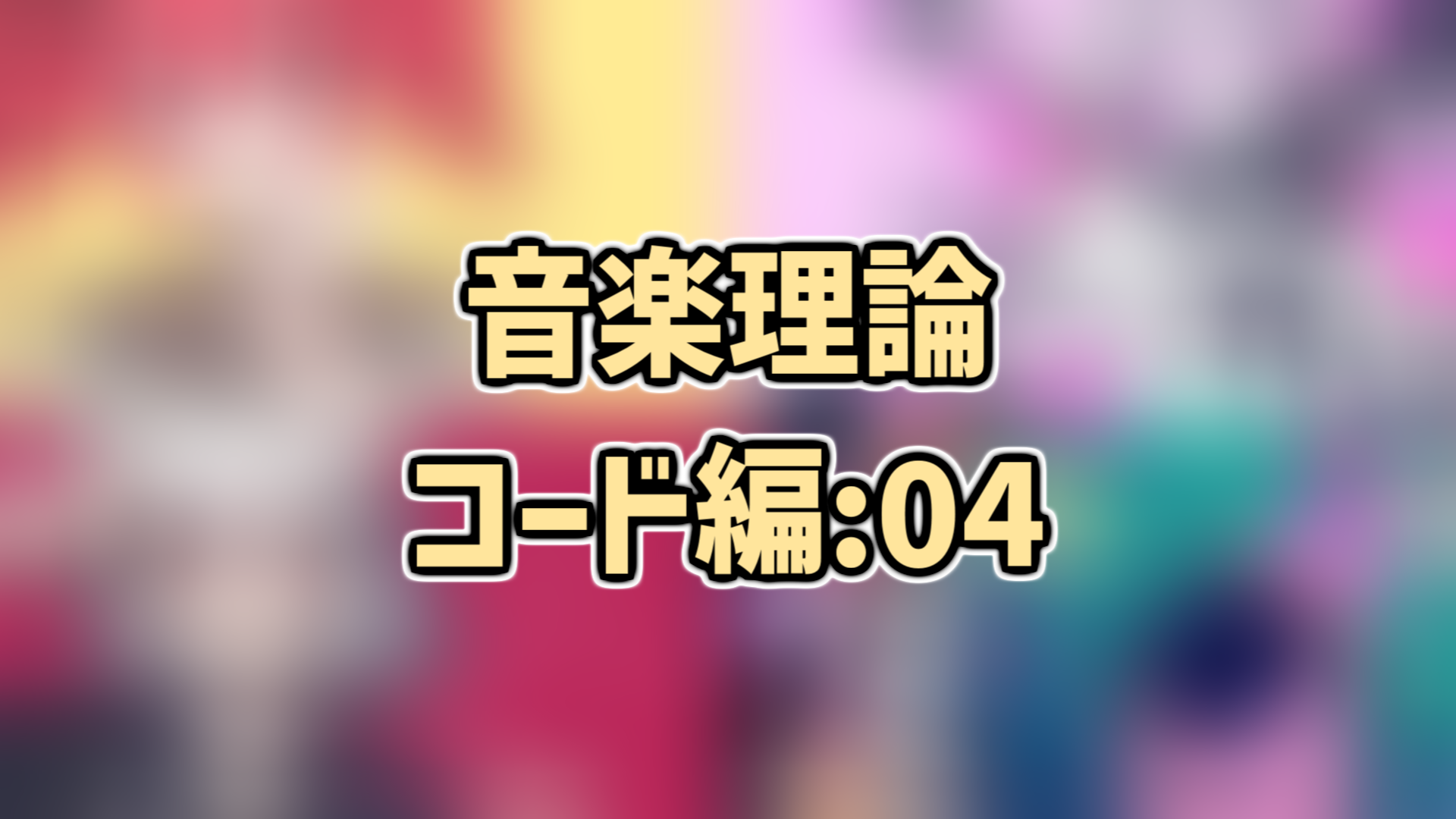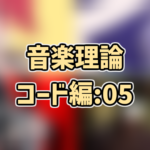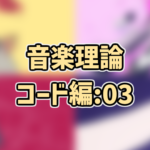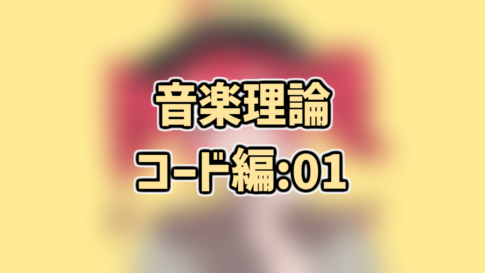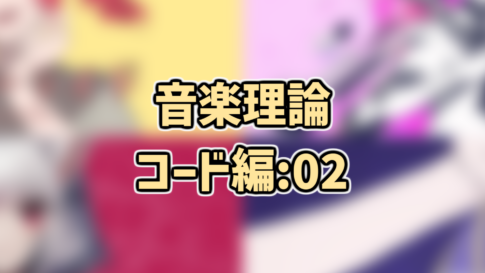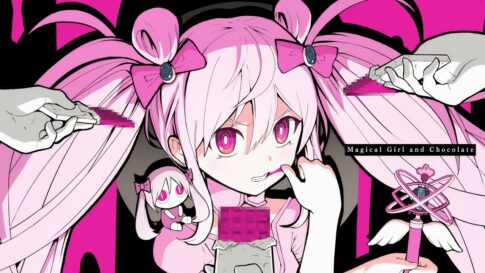皆さんごきげんよう。IWOLIです。
ボカロ曲で学ぶ音楽理論シリーズ
今回はコードそのものというより、
コードが曲の中で持つ3種類の役割について解説します。
僕はコード理論の中でここが一番の要だと思っています!
少なくとも僕は、ここを理解した途端にコードやコード進行というものが分かる様になっていったので、
今まで分からなかったという方も少しでも理解へ近づけるようにここで学んでいっていただければと思います!
Contents
3つの役割:トニック・ドミナント・サブドミナント
早速その3つの役割が何なのかを解説していきます。
まずコードの役割は以下の3種類に分けられます。
- トニックコード
- ドミナントコード
- サブドミナントコード
これらは今まで解説してきた「メジャー」や「マイナー」などとは別の考え方で、
コードそのものの雰囲気ではなく、
そのキー内での役回りや立場を示すものです。
メジャー・マイナーが属性というイメージなら、
トニック・サブドミナントなどは主役・脇役というような例えが近いでしょうか。
そのため、同じトニックに分類されるコードの中には、
メジャーもマイナーもどちらも存在します。
以下がその対応です。
- トニック:Ⅰ・Ⅲm・Ⅵm
- ドミナントコード:Ⅴ・Ⅶm(♭5)
- サブドミナントコード:Ⅱm・Ⅳ
このようにコードの役割はメジャーなどの種類と関係なく、
そのキーでの度数によって決まります。
つまり例えばCメジャーなら、
- トニック:C・Em・Am
- ドミナントコード:G・Bm(♭5)
- サブドミナントコード:Dm・F
という構成になりますが、
例えばFメジャーキーの時は、
F=Ⅰ度 ですので、Fはトニックということになります。
例えるなら「Cメジャーコードは元気ハツラツな人」とか、
「Aマイナーコードはダウナーな人」が居たとして、
そんなCメジャーコードさんが
Cメジャーキーのストーリーなら1番目立つ主役、
Gメジャーキーのストーリーなら脇役、になるという感じでしょうか。
もちろんAマイナーコードさんも、CメジャーキーかGメジャーキーかによって役回りは変わってきます。
とにかく今は、コードの種類ではなく、
度数によってコードの役割が3種類に分けられるという事を覚えておきましょう!
何度がトニックとかは使っているうちに覚えるくらいで良いと思います。(ここで詰まっちゃったらもったいない!)
厳密に言うとこれはメジャーキーの場合の話で、
マイナーキーの場合は「マイナー」が付いたもの、
トニックマイナー、ドミナントマイナー、サブドミナントマイナーと呼ぶ方が正しいのですが、
ここではメジャーを基準に考えるため敢えて割愛します。ややこしいだけなので。
その都合、「Ⅰ」や「Ⅴ」だと分かりにくいかもですし、
ここからはメジャーコードも「ⅠM」「ⅤM」という感じに表記します。
主役・曲の基本になる「トニック」(T)
ではそれぞれの役割を一つずつ見ていきます。
一つ目はやはりトニック、そのキーにおいて基本となるコードです。略称は“T”
メジャーキーでは ⅠM・Ⅲm・Ⅵm がトニックに属します。
Cメジャーキーで言う、 C・Em・Am の3つですね。
これらの特徴はとにかくド安定、どっしり腰を据えた、
仁王立ちしているような(?)コードです。
そのため始まりがトニックだと安定感のある始まりになりやすい他、
曲やパートの終わりは基本これらトニックの仕事です。(例外アリ)
ⅠM
まずⅠM、こやつの安定感は抜群、まさに
「大団円!」「ハッピーエンド!!!」という感じが凄いです。
Ⅵm(T) – Ⅳ(SD) – Ⅴ(D) – Ⅰ(T)
授業のチャイムかな
最初はトニックのマイナーなので若干暗めですが安定していて、
特にメジャーで終わる最後は実家(というか母校)のような安心感があります。
逆にその極端な明るさからか、このシリーズのテーマでもある、
「ボカロ曲」に限って言えば、このⅠMを前面に押し出した底抜けに明るいものは少なめに思われます。
それこそシリーズで何度も擦り続けているオーバーライドとかはメジャー感が強いですが。
Ⅵm
逆にボカロなどにありがちな暗さ、
「ハッピーなんぞあるわけねーだろクソが」と言わんばかりの根暗な展開に向いているのがⅥmです。
ⅣM(SD) – ⅤM(D) – Ⅵm(T)
前半はメジャーコードなので明るいですが落ち着きや安定感が少なく、
むしろ「これからどうなるんだろう!?」という盛り上げ感が強いと思います。
そして最後に来るのがトニックのマイナーなので、安定感はありますが、
暗い所に落ち着いたという雰囲気の演出になります。
ボカロ界ではこのタイプの曲が余りにも多いのでどこから紹介しようかというレベルですが…
例えばモニタリングなんかは一例ですかね。
終わりがⅥmになっているので曲のテーマにもあったダウナーな終わり方になっています。
Ⅲm
3つ目のⅢmですがこちらはちょっと特殊です。
こちらを例えばCメジャーキーで構成音を見ると、
- Em:ミ・ソ・シ
となっています。
そう、
- C:ド・ミ・ソ
- Am:ラ・ド・ミ
と違い、ⅢmであるEmには、基本となる「ド」がありません。
キーの基準たるⅠ度がないため、このコードだけはトニックとしての役目が弱めです。
このコードで締めくくってしまうと、なんとも釈然としない終わり方になりがちと言われます。
「主人公パーティのメンバーだけどあまりパッとしない立ち位置」みたいな感じでしょうか。
敢えてこれで終わるテクもありますがあまり多くはありません。
またこのEmの構成音、 ミ・ソ・シ は
Gの構成音 ソ・シ・レ と共通点が多いので、
次に紹介するドミナントに近いとも言えます。
トニックに向かう動きを作る:ドミナント(D)
次に重要なのがドミナントです。
これはトニックとは対照的に不安定なコードです。略称は“D”
メジャーキーでいう、 ⅤM ・Ⅶm(♭5)であり、
Cメジャーキーで考えると、 G ・Bm(♭5)がドミナントに当たります。
Gはメジャーコードではあるので明るいんですが何故不安定なのか?
構成音を見てみましょう。
- G:ソ・シ・レ
- Bm(♭5):シ・レ・ファ
このように、ドと半音で隣り合う音、
「シ」が含まれていますね。
また先ほどのEmについても、
- Em:ミ・ソ・シ
となっています。
これらのコードは例えメジャーだろうとマイナーだろうと、
そのキーにおいては何か不安定で落ち着かない、
どこか安定した所に着地したいという雰囲気を演出します。
ⅤM
ドミナントの代表例がこのⅤM、5度メジャーです。
このコードを弾いた時点で、次はついついⅠMかⅥmに進みたくなってしまう、そんなパワーがあります。
例えば典型的なのがこれ。
Ⅱm(SD) – ⅤM(D) – ⅠM(T)
ラストで「決まったアアアアアア!!!!」って感じがしませんか?
特にこの「Ⅴ度→Ⅰ度」のキモチイイ流れを、
ドミナントモーションと言います。
正に大技が決まったような爽快感があるので、
曲のオイシイ所や最後のキメとして定番です。
勘のいい方はお気づきかもしれませんが、
先のトニックを解説した時もこのドミナントモーションがあります。
一つ目のこちらです。
Ⅵm(T) – Ⅳ(SD) – Ⅴ(D) – Ⅰ(T)
この最後二つが「Ⅴ度→Ⅰ度」の流れを取っているので、
とても自然で綺麗な流れに思えるんですね。
Ⅶm(♭5)
一方もう一つのこちらですが、
このⅦm(♭5)は少し使い辛いとされます。
ⅤMに比べてトニックに向かう力が弱いため、
使われるケースは限定的です。
Ⅱm(SD) – Ⅶm(♭5) (D) – ⅠM(T)
こう聞くと様になってる気もしないでもないですが。
バリエーションを作る:サブドミナント(SD)
最後のサブドミナント、
これはトニックのような安定でもなく、ドミナントの不安定感もない、
浮遊感という言葉で良く表現される役割です。略称は“SD”
メジャーキーで言えば、 Ⅱm・ⅣM が該当し、
Cメジャーキーなら、 Dm・F にあたります。
これまで、「トニックは安定」「ドミナントは不安定だからトニックに向かう」説明しました。
ただこれだけでは安定と不安定の2択行ったり来たりになってしまいます。
そこへバリエーションを持たせられるのがサブドミナント。
トニックだけじゃつまらないけど、ドミナント→トニックほどの力は要らないという時に使えるでしょう。
例えばドミナントに向かう前を
トニックの安定では無くサブドミナントにして、
「一体どこへ向かっちまうんだ!?」感を演出したり、
最初のコードをサブドミナントで始める事で、
敢えて主人公の日常ではない所で始める捻った導入にするなどの工夫が有り得ます。
ガルパン劇場版でダージリン様から始まるみたいな感じですね(ガルパンはいいぞ)
特に最初をサブドミナントにするコード進行は、
J-POP・ボカロ系ではもはやこれが基本と言わんばかりの使用頻度になっていますね。
Ⅱm
先に数字の若いⅡmから解説しますが、
基本的にサブドミナントと言えばⅣMが挙がる事が多く、
ⅡmはⅣMをメインにしていたコード進行の派生や変化形である事が多いでしょうか…
あまり強調や頻出はしない印象があります。
とはいえさっきも登場した以下のような進行はド王道です。
Ⅱm(SD) – ⅤM(D) – ⅠM(T)
特にⅡmはⅤMに向かう力が強く、
Ⅱm → Ⅴ → Ⅰ という「ツーファイブ」と呼ばれる進行は、
数あるコード進行の基本中の基本としてよく挙げられます。
ⅣM
さて、基本とされがちなⅣMです。
基本とあって実際に使われるコード進行では、
サブドミナントにこちらのⅣMを使っているケースの方がやけに多く思われます。
例えばさっきも出てきたこれ!
ⅣM(SD) – ⅤM(D) – Ⅵm(T)
そしてここでもサブドミナントはドミナントに向かっていますね。
トニックほど万能選手ではないですが、
それでも色んな所に差し込み展開を作りやすいのがサブドミナントと言えます。
スリーコードと代理コード
今まで紹介した、3つに分類された7つのダイアトニックコードですが、
その中でも各役割(T・D・SD)における主要なコード、
代表選手のようなコードと、
それ以外のコード、という分け方があります。
代表選手の方3つをスリーコードと呼び、
残る4つを代理コードと呼びます。
スリーコード
スリーコードの構成はそれぞれ、
- トニック:ⅠM
- ドミナント:ⅤM
- サブドミナント:ⅣM
の3つです。
トニック、ドミナントは良いとして、
サブドミナントの解説で、Ⅳの方が基本と言ったのは、
Ⅳの方がスリーコードとされているからなのでした。
代理コード
一方の代理コードは残る4つですね。
- トニック:Ⅲm・Ⅵm
- ドミナント:Ⅶm(♭5)
- サブドミナント:Ⅱm
代理と言っても劣るという事はなく、
スリーコードで構成されていたコード進行を代理させることで、
似て非なる新たな響きやストーリーを生み出せます。
スリーコードと代理コードの扱い
これらの区別、理論については解説でしばしば、
スリーコード基準で先に語られることが多いように思われますが、
これらは目的に応じてどちらを使っても問題ないと思っています。
例えばツーファイブを使ってみたり、
さっきもあったⅤM→Ⅵmの流れを取り入れたりなど、
柔軟に使ってみましょう。
じゃあなんで説明したかって?さっき「ⅣMの方が基本」って言った理由も言った方が良いかなってゴニョゴニョ…
まとめ
という事で今回は、コードの種類では無く、
役割という見方でダイアトニックコードを3つに分類して解説してきました。
無事付いて来れていますでしょうか?
このトニック、ドミナント、サブドミナントという考えを会得すると、
コード進行の正体も分かってドンドン曲作りが楽しくなっていきます!
是非身に着けていってくださいね。
次回はいよいよこれらの知識を総動員して、
コード進行というものをバラし、正体を暴いてやりましょう!!(そんな大げさなものではない)
ではオヤカマッサン!