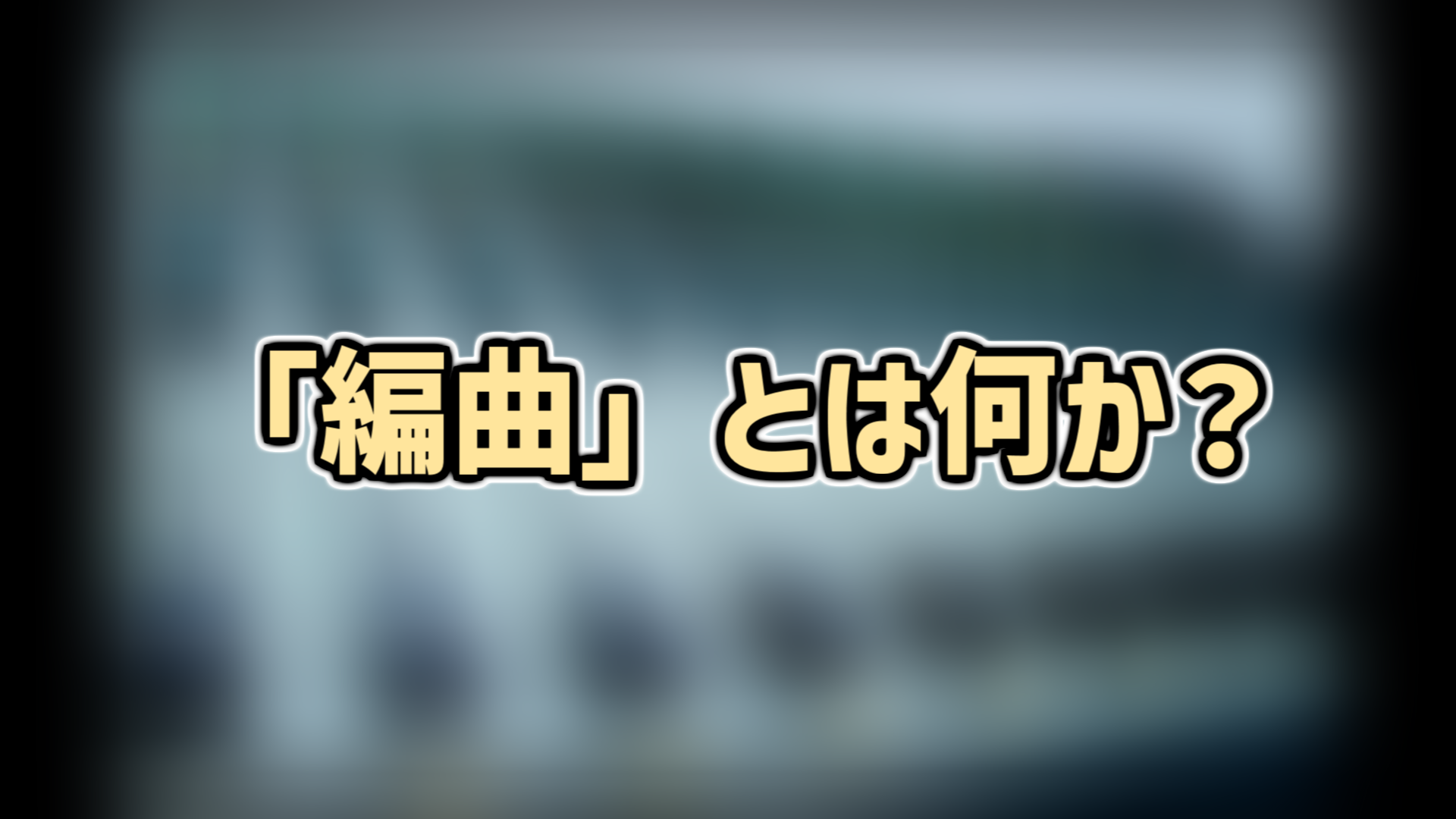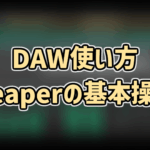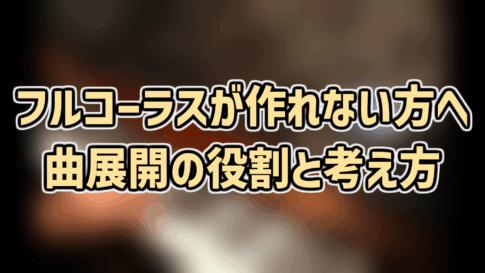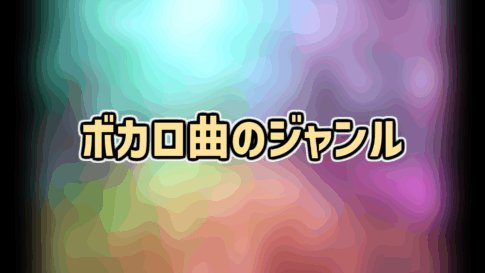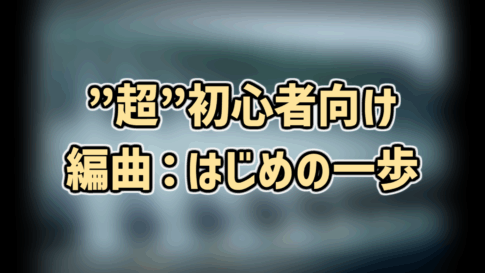皆さんごきげんよう、IWOLIです。
貴方は、編曲や編曲者について意識したことはありますか?
編曲は作曲者が編曲者も兼ねていることもあれば、
別の人が協力しているケースもありますが、
実際に編曲では何をしているのか、どのような効果があるのかについて、
あまり考えたことが無い方も多いでしょう。
今回は編曲のいろはということで、そもそも編曲って何なのか?
作曲とは何が違って何をするのか?という事を解説します。
Contents
編曲とは、音楽の「肉付け」である
まず僕なりの結論をお話しすると、編曲は「肉付け」という言葉がしっくりくるなと思います。
いきなり例え話で困惑したかもしれませんが、順番に解説しますね!
今回のお話の範囲
そもそも「作曲」や「編曲」という言葉は意味の範囲が曖昧で、
時代や言葉を使う人によってどこまで意味するかが変わったりする難儀な言葉です。
なのでまず前提として、今回お話するのはポップスやネットカルチャーに見られるような、
昨今たくさんのリスナーを沸かせる現代的な音楽で一般的な認識での話とします。
編曲は「世界観」を決める
現代において、「作曲」と呼ばれる範囲はその曲のメロディとコードを作る事と言われることが多いです。
そして「編曲」はその後、主に作曲で作られたメロディ・コードを、
どのように演奏し作品を演出するか?という部分を指すことが多いです。
その目標は、楽曲で表現したいテーマへ一気に迫るためです。
その中でコードの弾き方や構成に手を入れたり、
アグレッシブな展開を盛り込むことでメロディも変化させることも有り得ますが、
作曲で大まかに決まっていた軸に沿って彩っていき、
目指した世界観の大部分が形になるのが編曲と言えます。
逆にかつて音楽の基本だったクラシックにおいては、
編曲面も含めて作曲と言われがちなようです。
それはやはり、楽器がオーケストラでほぼ固定されているため、
それも含めて全部決める事を作曲としたのでしょう。
「アレンジ」と「リミックス」
さて編曲は「アレンジ」と訳されますが、
アレンジはよく「元ある形から変える」「再構成する」という意味で使われがちですよね。
ただ実はこれは英語での“arrange”の意味とは異なっており、
本来の“arrange”は「整頓する」「配列する」という意味だそうです。
そう思うと編曲が「配列・配置する」という意味で考えると、
「楽器を各パート・役割に配置する」と思えてしっくりきますね。
一方で「リミックス」という言葉を聞いたことがある方も居ると思いますが、
これは「作曲」の部分は出来るだけ変えず、「編曲」面だけを変えて、
楽曲を生まれ変わらせる事を言います。
正に「アレンジ(配置)面でのリメイク」ですね!(ややこしい)
良く知った曲でも、楽器構成がオーケストラ・ロック・ジャズ・EDM・サンバなどと変わるごとに、
例え歌やコード進行が同じでも全然雰囲気が違って聴こえますよね?
これも編曲の力です。
編曲って侮れないでしょう?
出来上がった音源のバランスや適切な音圧・音量感に関わる部分です。
とても大切な項目ではありますが、作編曲に比べて世界観やテーマを激変させるような工程ではないでしょう。
編曲は何をすれば良い?
編曲のいろはが分かった所で、具体的に何をするのか解説します。
作曲のみ出来た段階(まだ編曲されていない状態)というのは、
言い換えれば最小限の楽譜のみがある状態です。
という事は決まっているのは、
- キー
- テンポ
- メロディ
- コード進行
辺りという事です。
対する編曲とは、楽曲の構成要素の内、
作曲で決めていない物の大部分を決めることになります。
簡単に幾つか挙げると、
- 楽器構成
- 楽器それぞれのパート分けや演奏の仕方、配置
- 緩急・メリハリ・見せ場などの演出
といった感じになります。
順番に見ていきましょう!
楽器構成・パート分けを決める
まずは楽器に関して。これは分かりやすいかもしれません。
決まっている楽譜にある音を、何がどのように奏でるかという事ですね。
昔は曲を作ろうと思ったら演奏者が欠かせませんでしたが、
今はDTMが超お手軽な時代!世界中の楽器が使い放題です!(なお値段)
例えばエレキギターを入れたら力強い雰囲気になりやすく、
ストリングス、バイオリンなどを入れたら物憂げで大人びた演出が出来ます。
またそれぞれの楽器がどう演奏するかもかなり影響が大きいですね。
同じピアノの音でも、ロングトーンを単音で奏でるのか、
コードでかつリズミカルにバッキングするのかで全く違う雰囲気になります。
果ては同じ楽器でも音色の違う音源や奏法など、
楽器のことだけでも選択肢はかなりの数です。
考えることが多く大変ではありますが、逆にその引き出しが多ければ、
幅広い表現が出来てとても楽しいですよ!
緩急・メリハリ・見せ場を作る
更に踏み込むと、楽曲のメリハリ、緩急や見せ場などを作るのも編曲の醍醐味でしょう。
例えば曲のテンション・盛り上がりが最初から最後まで一定の曲は少ないでしょう。
有名な曲なら猶更、
- 期待感を煽る
- 盛り上げる
- 落ち着ける
といった、場面ごとの演出やメリハリ、緩急がある場合がほとんどです。
即ち曲展開を作る必要があるという事。起承転結みたいな感じです。
これは作曲の時点である程度固まっていることもあると思いますので、
作曲・編曲の両方からアプローチしていくことにもなるでしょう。
例えば”ここで曲を盛り上げたい”という箇所があったとします。所謂サビですね。
その際に作曲的にアプローチするなら
- メロディの動きをダイナミックにする
- キャッチーなリズムモチーフを繰り返して主題をアピールする
- 印象的なコード進行を使う
- 「ダダン!ダダン!」といったキメのリズムを作る
などが考えられます。
一方の編曲面でも例えば、
- 楽器の数を増やす
- ドラムのリズムを変える
- キレの良い音で疾走感を出す
- メインのメロディとは別のメロディを小さく入れる
- すべての楽器をキメに合わせてインパクトを出す
といった手法で盛り上げる事が出来ます。
更にはここに挙げきれないような細かい制御で、
楽譜には表しきれないような演出・展開をすることもありますね。
まとめ
という事で今回は編曲の基本として、
そもそも編曲は何を指し、何をするのかを解説しました。
編曲は作品を作る上で、作曲に勝るとも劣らない重要な工程です。
これから編曲に関することも解説していきますので、頑張っていきましょう!
それではオヤカマッサン~