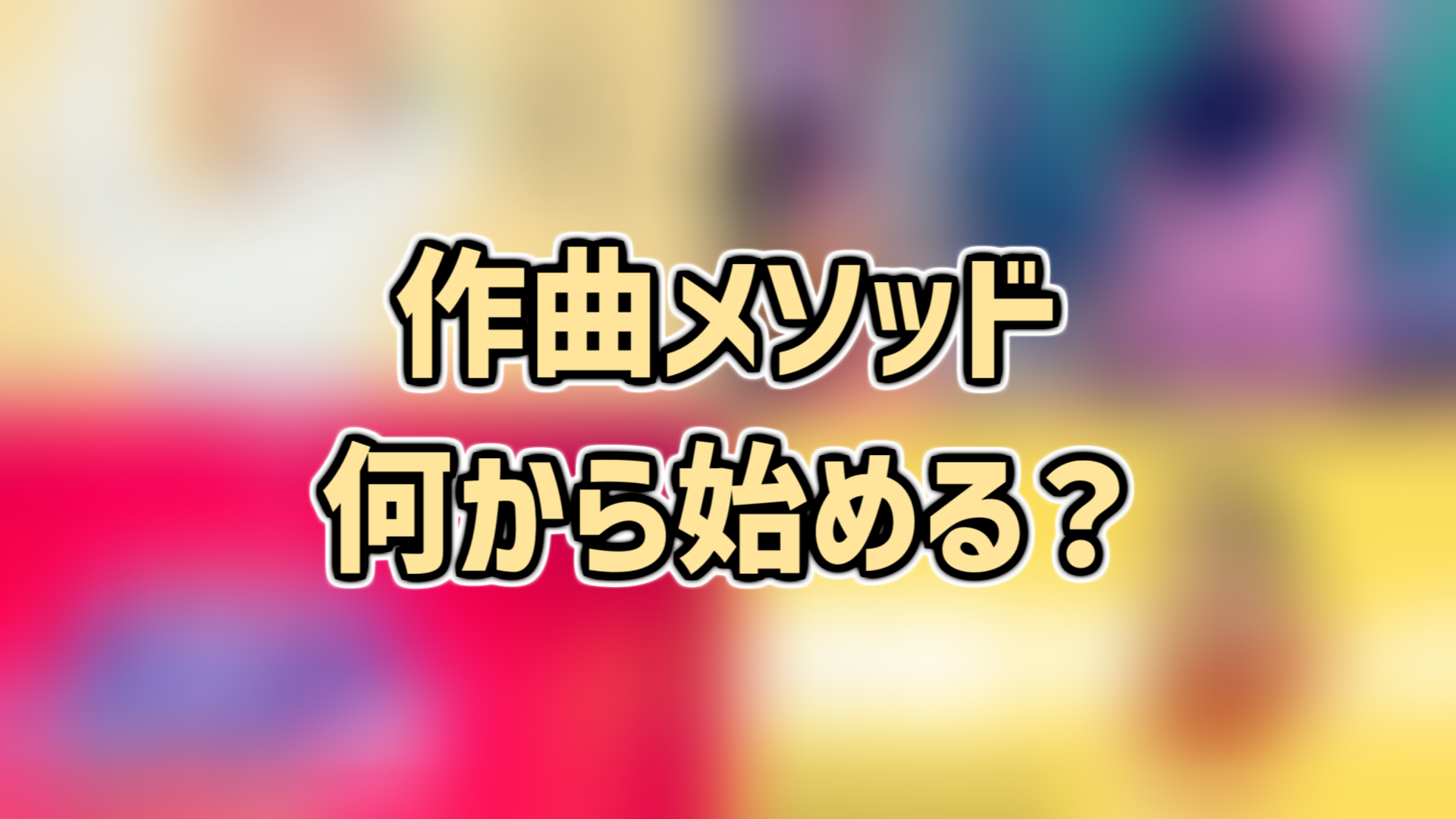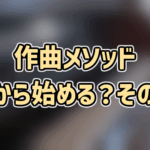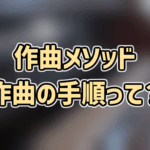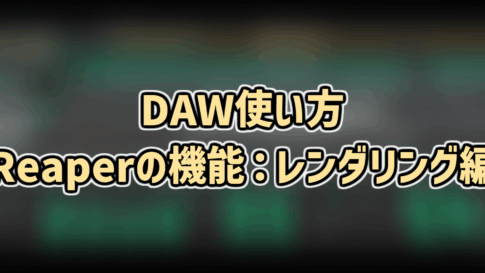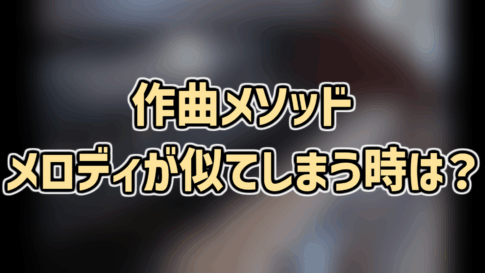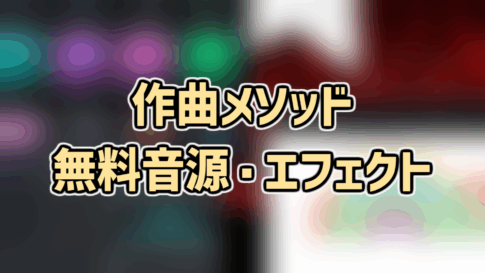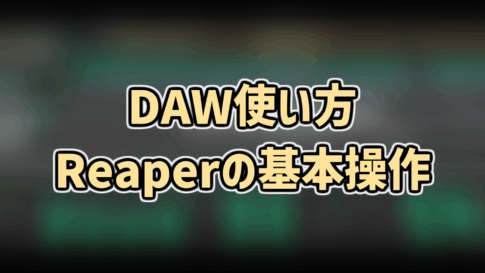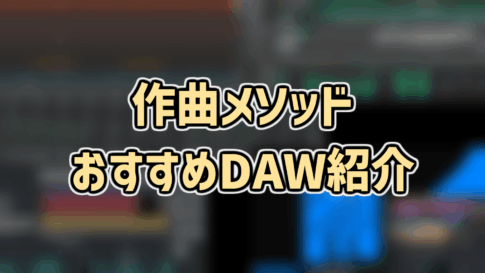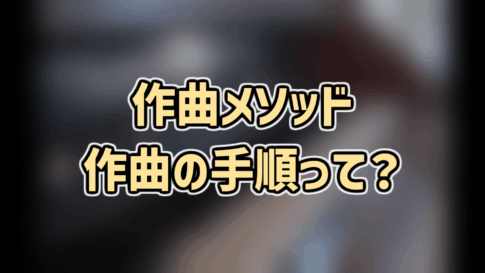皆さんごきげんよう。IWOLIです。
今回は作曲を始める時に一番始めにすべきことについて解説します。
それは、「〇ー〇」から決めるという事です。
「コード」でしょうか?いいえ、確かに間違いでは無いですが、
ここではそういった音楽に直接繋がる様な話はしません。
ですが意外と大切な部分だと思いますので見ていきましょう!
Contents
一番始めに決めておくと良いこと
では早速この答えを言ってしまいましょう。
始めに決めるべきことそれは、「テーマ」です。
別に音楽の専門知識という事ではないですよね。
これは音楽どころか芸術にさえ限らず、
何かアクションを起こそうとする時には必ず大切になってきます。
何かイベントやキャンペーンを開催する時、
例えば24時間テレビみたいな大々的な企画をする時でも、
はたまたYouTubeなどで継続的に動画を出していく時でも、
これらを通して「何がしたいのか」を明確にします。
「愛は地球を救う」なんて印象的でしたよね。
他にも何かガジェットを紹介する動画なら「〇〇に使えるコイツの良さを伝える!」というテーマになるでしょう。
テーマというと抽象的で分かりにくいかもしれませんが、
これは音楽においてもとても大切です。
ここはひとつ、ボカロなどの有名曲を例に見てみましょう。
有名曲のテーマを考えてみる
では幾つか有名曲を挙げていきます。
直接的で分かりやすいテーマ
まずはこちら、Chinozoさんからグッバイ宣言。
こちらはやはりコロナ禍でステイホームが叫ばれている中のリリースという事もあってか、
物凄い勢いで伸び流行ったのが印象的でしたね。
その一番の理由は何と言ってもやはり、
この歌のテーマがサビ冒頭にある、「引きこもり絶対ジャスティス」に込められているからだと思っています。
みんなコロナを恐れ、感染は怖いけど家の中に籠って辛い寂しい、という思いを、
この明るい印象も強い歌で吹き飛ばすような、
「引きこもりがなんだ最高じゃないか!」と言わんばかりの、
テーマに合致した歌詞や曲調がリスナーの心をつかんだ好例と言えるでしょう。
極端な主観や心理にフォーカスしたテーマ
お次に見ていくのはDECO*27さんの名曲モニタリングです。
こちらは少し変則的かもしれません。
歌詞とサムネイルだけを見れば、
アパートの一室に住む主人公をドアスコープから覗いて監視するストーカー少女のストーリーに思えますが、
それを否定できる唯一と言えるアリバイが、
途中から度々差し込まれる「普通に心配して部屋に来ただけの少女」です。
やはりボカロ界隈のリスナーは鍛えられているだけあってこの歌の解釈は、
「心配や何らかの伝達などで訪れただけの少女に対し、
勝手に独りよがりで変態的な妄想を膨らませてしまっている主人公」という解釈でほぼ満場一致しています。
「狂っているのは主人公?」というテーマを、
歌詞全てを完全に主人公主観の妄想で埋め付くすことで、
この世界観への没入感や、主人公の気持ち悪さが浮き彫りになる、
なんともDECO*27さんらしいリリックですね。
特殊な人への解像度が高過ぎるテーマ
お次は(ボカロ出身ではありますが)ボカロ以外から、
米津玄師さんの伝説、KICK BACKです。
いつ聴いてもかっこいいですねぇ。
この歌は「チェンソーマン」のOPとあって、
主人公のデンジにかなりフォーカスしていると思います。
様々な解釈がなされていますが、この歌には「ハッピー」「ラッキー」というワードがかなり重要になっているでしょう。
チェンソーマンのデンジは両親の借金からとんでもなく不幸な人生を強いられてきています。
米津さん本人が言及されていたことですが、こういった幸せに程遠い経験しかない人は、
幸せに至る方法や幸せというものへの理解や解像度が低くなってしまい、
ただ「幸せになりたい」という漠然とした願いしか持てなくなる、とのことでした。
「なんでそんなこと分かるんだ…」と思えるほど、
今まで想像もできなかったけど何となくそうだと思えてしまう言葉ですね。
KICK BACKはそんな不幸のどん底に居るデンジ目線で、
ひたすら形の見えない幸せを盲目的に追っている歌の様に思えます。
特に具体的過ぎてかつユルいテーマ
最後に物凄く方向性が違う曲を見てみます。
Yukopiさんの盛大にバズった強風オールバックです。
ボカロ界ではしばしばこういった、
笑いやシュールさを追求したナンセンスさが売りの「ネタ曲」が流行りますが、
この歌はそれが特に大当たりを決めたパターンと言えるでしょう。
「こんなユルい歌にテーマなんて」と思うかもしれませんが、
この歌は兎にも角にも「向かい風が強過ぎて前に進めない」という、
「そうはならんやろ」と言いたくなるような状況を叙事的に表現した例と言えます。
これだけでもシュールなのに歌い出した、
「外出た瞬間」→「 終 わ っ た わ 」
と始まった瞬間終わりを悟る悲壮感のインパクトが凄いです。
更に続く歌詞や、向かい風なのにずっと歩こうとしている少女の愚直さや諦めない心が、
何も考えていなくても何か訴えかけられるものを感じます。
人気曲のテーマの共通点
これらの名(迷?)曲にはどれも、とても明瞭で具体的なテーマが存在します。
グッバイ宣言はただの「引きこもりの歌」ではなく、
「引きこもって音楽を謳歌するサイコーな生活」。
モニタリングはただの「ストーカーの歌」でも「妄想癖の歌」でもなく、
「自分の為に来てくれた好意があるとも限らない少女に、勝手に自分好みの妄想を貼り付けて気持ち良くなっている気持ち悪い主人公」。
KICK BACKは「不幸な主人公の歌」ではなく、
「不幸過ぎて幸せの片鱗も知らない少年が、がむしゃらに幸せを追う歌」と言えるでしょう。
少なくともこれらの歌においては、
この物凄く詳細で解像度の高いテーマがあったからこそ、
置かれている状況・シチュエーションや人物の心理がありありと伝わってきて没入感を生んだのだと思います。
もちろん、ここまでテーマを詰める事だけが正義とは限りません。
むしろ「何言ってんだ…?」と思わせるような歌も人気を読んだりします。
分かりやすいのがこちらでしょう…。
ほんとうにわけがわからないよ。
ご本人が解釈や解説を話されてはいますが、それでもわかりません。
https://note.com/sasukeharaguchi/n/n66e19d9dfd47
言葉同士の脈略の無さ・繋がらなさや一貫性の無さのために、
解釈や考察を見ても結構ブレがありそうです。
少なくともこの歌は明瞭なテーマではなく、
むしろ不可解しか起こらない、
いわば次何が出るか分からないホラーから目が離せなくなるような没入感がキモになっていると思います。
テーマを決めておいた方が良い理由
さてここまで、世の中を席巻するような名曲を上げてきましたが、
「こんなハイレベルなテーマ無理だよ!」とも思われるでしょう。
そりゃそうです、あの方々はちょっと次元が違います。
ですが例え初めてでも、大量の再生が見込めなくても、
テーマを可能な限りはっきり決めておく方が良い理由が、
今後の作曲の指針として大活躍するからです。
以前の記事で紹介しましたが、
この先作曲を進めていく中では結構色んな工程が立ちはだかります。
更に各工程の中ですべき判断はとんでもない数です。
「次のコードは何が良いんだろう?」
「次のパートで何を言えばいいんだろう?」
「この楽器構成で良いんだろうか?」
様々な疑問が湧いた時、テーマが定まっていないと、
「まあこれで大丈夫だろう」と決めたとしても、
その構成要素同士がバラバラになってしまい、
最終的に何がしたかったのか良く分からないものが出来上がったりします。
むしろ、出来上がったのなら御の字かもしれません。
最悪の場合、次に打つべき手が分からず、
「明らかに未完成だけど手も出せない」というどうしようもないものが生まれてしまうリスクもあります。
時折、「歌を作るならサビから」という考えを目にしますが、
これはまさに、その歌のテーマが最も色濃く表れる場所こそが、
最大の見せ場になるサビだからだと思っています。
言い換えると、テーマが完全に定まっていれば作りやすい所から作る事も出来るとも言えますね。
実際に拙作アナザーランドではテーマを先に決めていたので、
サビの一部を考えてからはAメロやBメロ制作に移るなど、
結構ばらけた順番で作りました。
テーマの決め方は自由
とはいえそんなことを言われても、
最初は何からテーマを決めれば分からない事もあると思います。
ですがこれは頭を柔らかくすると意外と簡単に考えたり、
自由な発想でテーマを生み出せたりします。
ここではいくつかの例を紹介しますね!
テーマ例①実体験を基にする
一つ目はとてもシンプル、作者たる自分の実体験をもとに考えるというものです。
ある意味、日記だとか小学生の頃に夏休みの宿題に出された感想文に近いかもしれません。
こう思うと苦手だった人も多いかもですが、
ここで大事なのは「大きく感情が動いた体験」を「何故・どのように伝えたいか」という事です。
逆に言えば例えば修学旅行に行ったとか、なんかのイベントに参加したという体験があっても、
貴方がそれに対しこれといって感情が動いていないなら、テーマには不向きです。
むしろ一見なんの変哲もない日常だけど、感情がなにかざわついた思いや、一瞬の出来事でも歌のテーマたり得ます。
例えば好きなゲームで「あと一人打ち倒せば勝てる!」という時の緊張感と高揚感でも良いですし、
話しかけようとした人に「フッ…」と目を逸らされてしまった時の、怒っては無いけど何か物申したくなる感情でも良いでしょう。
或いは、何らかのセンセーショナルな作品に出会った時の衝撃かもしれません。
それについては次の項目で!
テーマ例②既存作品から派生する
二つ目は既に世に出ている作品から派生させるというパターンです。
一見するとこれはオリジナルではなく二次創作だと思えるかもしれませんが、
意外とこれはオリジナルとしてまかり通ります。
典型的なのがYOASOBIの代表曲、夜に駆けるです。
この歌はなんとタナトスの誘惑という小説を原作に作られた歌のようです。
またヨルシカさんの楽曲には小説が元になった物も多いですね。
小説以外だと、これはあくまでファンの考察、仮説に過ぎないようですが、
いよわさんのきゅうくらりんが、
ドキドキ文芸部!というゲームに登場するサヨリを元にしているのではないか?と言われていますね。
このようなスタンスで名曲が量産されているわけですし、
我々もこの手法を取らない手はないでしょう。
むしろ誰かの作品にインスピレーションを受けて、
自分なりに新たな何かを表現するというのは、
やってない人の方が少ないくらい普通の事です。
きゅうくらりんの様にゲームのキャラクターを元にしても良いですし、
なんならこの歌の様に誰かの歌を元にして新たな歌を作るという事も考えられます。
あまり露骨に元ネタの要素が残り過ぎていたり、
新たに付与された独自性が足りないと、
リスナーがその作品固有の物を見いだせず、
パクりや盗作と認識されてしまう恐れもありますが、
〇〇(アーティスト)に似ているとか、
〇〇(作品)っぽいという評価は気にしなくて良いと思っています。
再生数1000万回を優に超えるきゅうくらりんが、
「サヨリか」と言われているぐらいですからね。
テーマ例③いっそ歌詞関係無しで考える
三つめは今までとかなり方向性の違う考え方です。
またこれは歌詞の無い、インスト曲を作る時に特に有効になるであろう方法ですね。
それは、いっそのこと今まで考えてきたようなストーリー性以外でテーマを考えるというもの。
何かを表現するのではなく、
どんな楽器で表現するかとか、このジャンルに挑戦してみるといった、
音楽的に表現の手段から方向性を固める方法ですね。
これは初心者向けとは言い難い所もありますが、
例えば新たな事にチャレンジしたい時や、
逆に取り敢えずなんか作ろう、作曲の為に動こうという時に良いでしょう。
また完全な初見の場合は明確なテーマを定めるのが難しいという理由で、
「取り敢えずサビっぽいものを16小節だけ作ってみる!」
というのも十分テーマにできそうです。
完成したらあとはテキトーに乗せる歌詞をぶちまけたネタ曲にしても良いですし、
ボーカルサンプルを利用すればそれだけでボーカル曲っぽくもできます。
「なんも思いつかない!」という時にこそ、敢えてこのやり方を取るのもありかもしれませんよ?
まとめ
今回は作曲を始めるにあたり、意外にも一番大切な、
テーマという部分について深掘りしました。
凄く大事でありながら、凄く難しい部分でもありますが、
これの有る無しで後の作業難易度がかなり変わってくると思いますので考えてみましょう!
またテーマという部分は音楽的な音程とかコードとかがまだ関わっていない、言葉だけで表現できる部分です。
つまり楽器やDAWなど曲を作るための環境にいなくても、
ちょっとした情報や他愛もない会話がテーマになる事もありえます。
むしろこういった部分は作業環境に引きこもっていない時の方がフレッシュに考えやすかったりすると思います。
実際に僕のテーマが湧きやすい状況は、例えば
- 食事中
- 風呂の中
- 寝る前
- 「音楽を聴かずに」移動している時
などなど、意外と音楽に触れていない時の方が思いつきやすかったりします。
今回の内容を参考に、試しに「自分は何が作りたいのか?」という問いに答えてみてください。
それではオヤカマッサン。