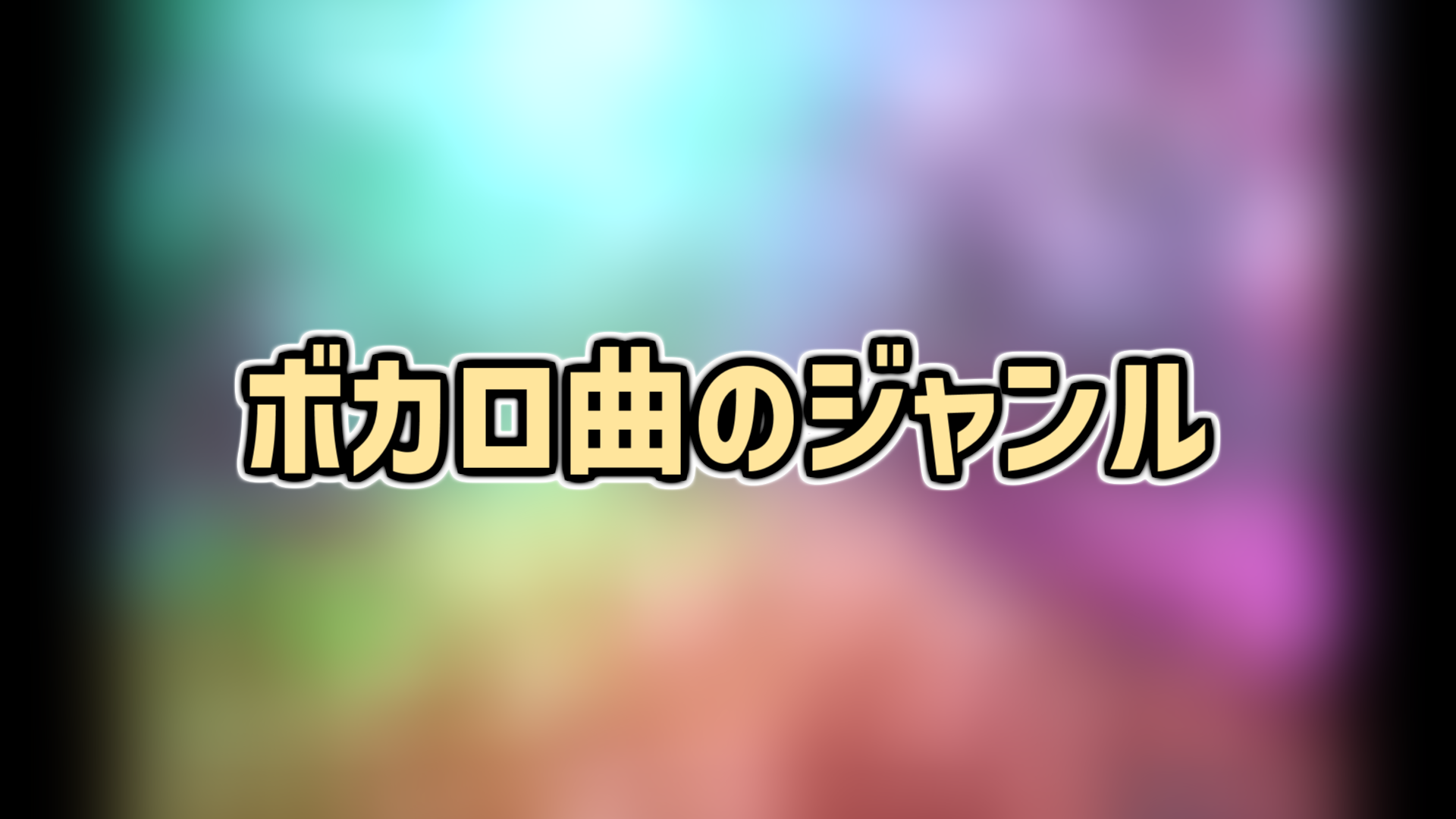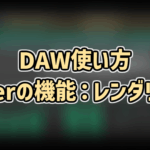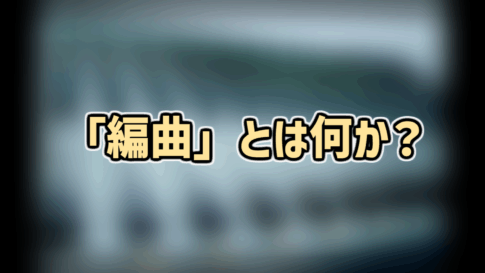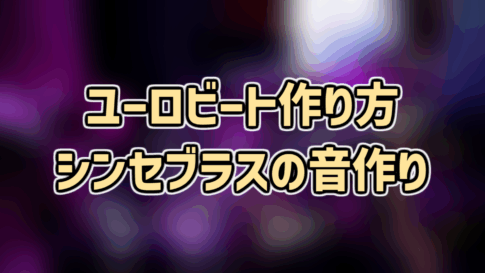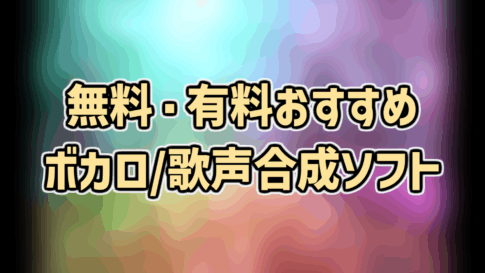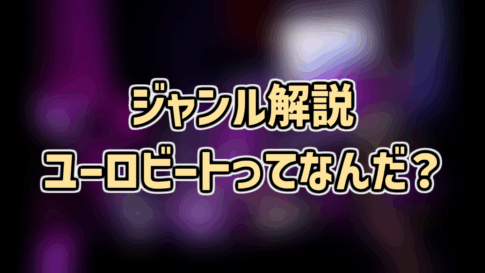皆さんごきげんよう、駆け出しボカロPのIWOLIです。
皆さんは「ボカロ曲のジャンル」って意識したことはありますか?
「”ボカロ”っていうジャンルじゃないの?」
…それもそうなんですが!
同じボカロ、歌声合成を用いた楽曲にも様々なスタイルがあります。
ポップで明るいもの、とにかくダークでシリアスなもの、
パワフルな曲、優し気な曲…。
これらは必ずしも名前があるとは限りませんが、
ボカロ以外の音楽への見方を応用すれば、ある程度なら分類でき、
「ボカロの中でも〇〇な感じの曲」というのが表現できると思っています。
今回はそんな、僕が思うボカロ曲の分類や傾向について紹介します!
大まかな分類とジャンルの聴き分け
ではまず、様々なボカロ曲を分ける時の大まかな種類と、
その基準や聴き分け方について解説します。
僕は音楽を分ける時、一番ざっくりとするなら
- アコースティック・バンド系
- エレクトリック・電子音楽系
- ハイブリッド・変則系
に分けるかなと思います。
アコースティック・バンド系
一つ目のアコースティック系やバンド系は、
ピアノやギターなど、生楽器が大部分を占めるスタイルです。
ボカロックなど、ロック系のものは典型的ですね。
ただ、ボカロックがわざわざ「”ボカ”ロック」と付けられている辺りからも、
単純なバンド構成とは言い切れない傾向を表していると思います。
後述の参考例で詳しく解説しますね!
エレクトリック・電子音楽系
二つ目のエレクトリック・電子音楽系は真逆で、
多くの音を電子音が占めているスタイルです。
エレクトロ〇〇とかテクノとか、ユーロビートもこれにあたりますね。
と言っても、ボカロ以外の電子音楽・クラブミュージックにおいても、
生楽器が結構目立つように配置された音楽や、
何なら一見生楽器メインに見えるけど、土台たるドラムなどが電子音ということは少なくなく、
ボカロにおいても「生楽器も入っているけど基盤が電子音だからエレクトリック」
という解釈があってもいいのかな?と思います。
ハイブリッド・変則系
最後は、これまでのような曖昧な判断をもってしても、
「それでもどっちとも言えなすぎる!!!」という、まさにその他スタイル。
またの名を変則、或いは変態的ともいえるジャンルです。
「なんでもありじゃねーか!」と言いたくなりますが、ボカロPに言ってください…
ホンマに自由過ぎます。それでいて良い曲で中毒性があり、
恐ろしいほどに伸びるんだからボカロとは奇怪なものです。
こちらもこの後参考曲を交え、何故ここに入れたか、
というより何故ここにしか入れられないかを解説しようと思います。
ジャンルの聴き分け
さて、3種類の簡単な分け方を整理した所で、
ここから実際に有名なボカロ曲を幾つか分類してみようと思いますが、
その際の基準についても詳細に説明します。
僕は曲のジャンルを聴き分ける際に一番最初に判断するのはドラムです。
その最大の理由は、作者が明記したジャンル名とほぼ毎回一致するのがドラムだからです。
例えば自分はロックを作ったという方は、例え打ち込みでも生ドラムのキットを使用しており、
サンプラーに充てられるような電子音のサンプルやブレイクビーツは稀です。
一方で明確なクラブ系のジャンルを想定していたり、特に定めていないという人は、
ドラム以外にどんな音を使ったとしても、キックはHouseに使われる電子的な物だったり、
キック以外のドラム音が例えばTrance系など、電子音が紛れ込んでいることが多い印象です。
逆に土台ではなく”ウワモノ”と呼ばれる音、リードやコード楽器は非常に自由度が高く、
特に電子音楽ではボカロに限らず何でもありですらあったりします。
ドラムと同じく土台にあたるベースでさえ、電子系なのにスラップベースを入れる人も居るくらいなのでこっちも信用できないでしょう。
またもう一つの理由が、基本としているリズムがジャンル判断に役立つからです。
特に電子音楽に顕著ですが、それ以外にも当てはまる事はありますね。
例えば四つ打ちならBPMによってHouseやTrance、Hardcoreの傾向が見られるな…とか、
幾つかのありがちなドラムパターンを切り替えているからロックで間違いなさそうだ、とかですね。
ドラム以外にヒントがある事ももちろんありますが、大まかな絞り込みにおいては重宝するでしょう。
それではお待たせしました、色んなボカロ曲を聴いていきましょう。
アコースティック・バンド系
まずはアコースティック・バンド系にあたるであろうボカロ曲です。
Rock(ロック)系
アコースティック1つ目はやはりロック寄りから。
特に相当典型的なのはこちらでしょう!
こちらゴーストルールに始まるDECO*27さんのメタル系3部作、
ゴーストルール・ヒバナ・キメラは間違いなくバンド系、
というよりその中のハードロックやヘビーメタルまで絞り込めそうです。
編曲のNaoki Itai氏の技量も相まって、最早「ボカロックというよりロック」とすら言えるほどにロックです。
普段はよくRockwellさんが編曲されているイメージがあります。
お次は特殊な音も加わって個性的なボカロック系!
イントロのギターリフなども相まって、普通にロックだと思われている方も多いと思われますが、
結構細かく不思議な効果音が入ったり、細かくカットアップされていたりと、
「ギター弾けるけど弾くだけじゃつまらない」と言わんばかりの手数が特徴です。
またこの後の作品であるダーリンダンスでは、この効果音感や、
特殊な音の演出に拍車が掛かっております。
ここまで行くと流石に「これはロックなのか?」と思えてきますが、
さっき述べた通り土台のドラムを中心に、軽めのギターサウンドなど、
まだロック要素が残っているということで僕はこれもボカロックと解釈しています。
ロック系最後にはさらに個性的になります。(?)
聴けばメインリフなどはギターの音はしているのですが、
かなり機械的に「テロテロ」と鳴らされており、メロディの不安定さもあって
とても「異星人襲来!」って感じですよね。
かいりきベアさんとは異なりナユタン星人さんはギターを打ち込みで作られているらしく、
それ故に生演奏では出ない機械っぽさ、「ギターだろうけどギターっぽくない」感が、
この歌で良い方向に吹っ切れている印象です。
楽器構成は大体ロックですが、ロック畑の人が見たら「え?」ってなるんでしょうね…
ポップ、アイドル系
さて、ボカロと聞いてもこれをイメージする方は結構多そうですね。
ポップ、即ちキャッチーで明るく聴きやすい、正にアイドルが可愛らしく歌っているような曲調ですね。
といってもこれをアコースティック系に入れるのは迷う所ではありました。
確かにアイドルらしい曲は、ロックを土台にしているケースも多くあるのも事実です。
懐かしいですねぇ…メランコリック
エレキギター・エレキベースなどかなりロックサウンドが占めてはいますが、
可愛げのあるシンセが耳を引くのもあって、ボカロックとポップの間という印象でしょうか。
ただ一方で、ボカロにおけるアイドルらしい曲は電子的なものも多いです。
鬼の調声(調教)と名高いMitchie M氏の名曲ですね。
この歌は辛うじてキックが生ドラムなのかな…?という感じではありますが、
生楽器っぽい音は「ドラムとピアノ以外おる?」というくらい電子音の嵐です。
ボカロという機械的なイメージと結びつきやすい影響かもしれませんね。
アイドルらしいかと問われると、歌詞的に疑問ですがこちらも当てはまるでしょうか。
…まぁ、少なくとも曲調はすごくかわいいですよね。
この曲も、ドラム・ピアノなどの生楽器は存在する一方で、
物理的にこの音は出せねぇだろ見たいな音が大半の帯域を埋め尽くしていますね。
身も蓋もない話ですが、そもそもこういったポップ系やアイドル系と呼ばれるもの自体、
「こんな構成をしている」という基準無しに、作り手聴き手の感性で決められてしまうので、
生・電子以前にジャンルとして議論して良いのかどうかも謎です…
ただ「こういうの、あるよね」と思い、
他のジャンルには入れようが無いけど可愛げのあるものだけをピックアップしました。
ジャンルミックス系
「3つ目にしてもう混ざってんのかよ」とか言わないでください…
ボカロってあまりに自由過ぎて、「純然たるこのジャンル!」が言えない曲がただでさえ多く、
アコースティック系ともなれば「打ち込みでそのジャンル感、キツくね?」ということなのか、更に拍車が掛かっている印象です。
オーバーライドでも有名な吉田夜世さんの楽曲。僕も好き
非常に爽やかなサビが印象的ですが、ドラムに注目してください。
冒頭は後述するドラムンベース系のリズムで、ギター以外は電子的なのですが、
0:21でフィルインが入ってから、ギター以外ほぼ全ての音がガラッと変わり、
一気にロック調にシフトしているのが分かりますか?
サビではシンセもあれど、やはり大部分がロック寄りなことが、
世界観を変える力を後押ししているようです。
更に強烈な例も見てみましょう。
れるりりさんの伝説、脳漿炸裂ガール。
この曲の何が個性的って、区間によって最早別物レベルでジャンル感、楽器構成が変わる事にあります。
和楽器が入ったと思えば、急にジャズチックになり、更にチップチューンに切り替わっていくという、
今でいえば半分FullFlavor(色んなジャンルを混ぜたジャンル)のような展開です。
というよりそういうジャンルミックスの中でポップだったのが先ほどのジャンルですが、
ポップとは呼べず、どのジャンルとも言い切れないのもあるのがボカロなんですよねぇ…
その他アコースティック系
もうその他になってしまいました…
調べの足りなさもあるとは思うのですが、多数のボカロPから
生楽器でなおかつ特定の単一ジャンルだけで構成された曲、
例えばジャズなどが作られているケースというのは少ないんじゃないかと思っています。
という事でまずは「ボカロジャズ」と言えば(だと思っている)方を
挙げて思ったんですがこれがジャズだと気付いてる方ってどれくらい居るんでしょうか?
GYARIさんはボカロでジャズを作り続ける方ですね。色気あるサウンドが良き…
ただこんな感じでボカロジャズが作れる方って他には…
鬼 変 拍 子
ただやはり、ロックやアイドル系の様な、或いは後の電子系みたいに、
沢山の人が作っている感じではないのかな…と思います。
続いては独特な世界観がある方向性です。
ひたすらにエモい!とにかく綺麗なサウンドが物語を彩ります。
かなり生楽器がメインな中でも、アコーディオンが特に目立ちますね。
様々な音が重なり、「オーケストラでもジャズでもない西洋っぽさ」があります。
こちらも、似ていると言えるかもしれない曲はあります。
懐かし過ぎる…
更にテンポが落ち、ドラムというよりパーカッションになったことで、
より民族音楽っぽさが増した気がします。
独自の世界観・物語を表現する上で取られる事のあるジャンルのようですが、
こちらもそう多くはないスタイルだと思います。
さて、ここから暫く、「むしろ同様のスタイルで作れる人教えて」レベルで、
他に伸びた例を知らないジャンルのボカロ曲が続きます…。
KAITOの楽曲の中でも未だに最初に上がるんじゃないかというくらいの名曲。
リメイクでこんな繊細に歌えるようになったんですよねぇ…
かなりオーケストラっぽくもありながらしっかりドラムが居るのでリズムがはっきりしていますよね。
ただそこからドラムを抜いたオーケストラ主体でも、
「ボカロ曲の傾向」に挙げられるほどは作られてないんじゃないでしょうか…
そしてジャンルは更にマニアック(?)な方向へ…
こちらはフラメンコと言えば良いんでしょうか?
大人びて暗い雰囲気なのに何か情熱的な雰囲気が、
不思議なほどに思春期の精神性に噛み合っている辺り流石オワタPことガルナさん。
相当真似もしにくい編曲になっていると言えるでしょう。
エレクトリック・電子音楽系
さて、お次は電子音楽系に移りましょう。
元々「メンバーも楽器も無しで曲を作れる」の最後のピースの様になっているのがボカロとあって、
ボカロ界隈そのものが電子音に寄っているのではないか?と思っている所で。
今回紹介していても、思っていた以上に電子音が多く、
「ワイそこまで偏ってたっけ?」という感じでした。(まあ偏ってはいるんですが)
あと個人的過ぎますが僕が電子系メインなので単純に予備知識もマシです。
やっと紹介がしやすくなる…
House(ハウス)寄りEDM系
まずは今の電子音楽における主流であろうHouse系から。
House系と言ってもこれも一つにくくるのが憚られるくらい幅がありますが、
典型的だと思えるものを幾つか紹介します。
個人的にこれだ!と思えるボカロEDMがこちら、Reolさんのヒビカセです。
シンプルな4つ打ちに強いベースが合わさり最強に見える、いや最強。
また懐かしいのを引っ張ってきましたがこちらもでしょう。
時代の差から音量感・バランス感など結構差はありますが、
当時のポップなElectro Houseという感じですね。
更にダメ押し、2024年にどんなスタイルが生まれているか聴いてみましょう。
モニタリング、ものすんごい流行り方でしたよね。
「え?ホントに電子音楽?」と思われたかもしれません。
実際にはかなり生楽器の数も多いですからね。
ですがキックを中心にベースも含め土台が結構シンセ的なこと、
リズムも常に一定の4つ打ちになっていることから、
「生楽器を加えたHouse」という解釈でいます。
これが2020年代のスタイルとは言い切れないと思いますが、
少なくともこういった形に派生したものがある、と考えるのが良いでしょう。
他にも八王子PさんやMitchie Mさんなど、相当数の方が作られている印象です。
ElectroSwing(エレクトロスウィング)系
ボカロの電子系で、近年相当作られている様に思えるのがこのElectroSwing系です。
Wikipediaのボカロ(音楽ジャンル)にも載っているくらいですからね。
ただ例によって、ボカロ以外で聴く場合に比べるとやはり、
ボカロElectroSwingはだいぶ個性派揃いという印象です。
まずはボカロElectroSwingの代表格!
ElectroSwingと言えばかめりあさん!かめりあさんと言えばElectroSwing!
僕はPsyStyleの方が好きだけど。
この曲についてはほぼほぼElectroSwingの教科書の様な曲になっているかなと思います。
4つ打ちのHouseっぽいビートの上にベースもシンセ、
ただウワモノにブラスなどの生楽器が居て、
メロディなどを中心にスイングしたノリがある、という感じですね。
では、それと違ったスタイルだとどうなるでしょう?
僕はこの曲がそんなElectroSwingだと思っています。
どうでしょう?ブラスではなくシンセのリフになっていたり、
ピアノの方が目立ってジャズというよりどちらかというと「ピコピコ」していますね。
ただそれでも、
- エレクトリックな4つ打ち
- 全体を通してスイングしている
- シンセ音も入っている
といった特徴から、この曲もElectroSwingだと思っています。
先ほどのヒアソビに比べ、清潔さか潔癖の様な精神を感じさせる印象のあるElectroSwing、という感じがしますね。
さて、更に個性的なElectroSwingがあります。
こちらのElectroSwingとして最大の特徴はテンポが速い事かなと思います。
ElectroSwingは基本的にHouseを基調とした120~128くらいなのですが、
こちらエバはなんとBPM=141!
電子音楽的にはTechnoやTranceの領域になっています。
このスピードは結構限界に近いのではないかと思っています。
もう一点はやはり随所に差し込まれる奇妙な効果音でしょうか。
間奏の「ブウウウウン…」という謎のベースなど、とにかく不思議でちょっと不気味な世界観で統一されています。
これまでになかった、ワウの掛かったギターも不思議な魅力がありますよね。
Eurobeat(ユーロビート)系
出ましたEurobeat。電子音楽の中でこれだけは知ってるという人も多そうです。
ただ、最近は他ジャンルや独自路線の台頭からか、
バンバンボカロEurobeatが作られているとは思えない気がします。
Remixならあるんですが…
まさかの過ぎて笑いながら頭振ったっちゅーねん
Remixが作られ、そして人気になることを見ると、
やはり未だに根強いファンが居る事を実感させられます。
それでも、完全オリジナルで高い注目を浴びたと言えば、
ボカロEurobeatの伝説、Samfree氏の時代にさかのぼらざるを得ません。。。
つまりYoutubeを貼るなら転載しかないということだ()
いつ聴いても最高ですわ、亡くすには惜しすぎた…
蛇足ですが、ユーロビートはその言葉だけ異常に浸透したためか、
時折ユーロビートでは無い曲もユーロビートと呼んでしまうケースが見られると思います。
他の例えばHouse、Techno、Tranceなどのジャンルとその区別が付いていないと使い分けられるはずもないので仕方ないのですが、
少なくとも僕の見立てでは、最新楽曲でユーロビートに当てはまるものを見つけるのは結構難しいんじゃないかな?と思います。
Drum’n’Bass(ドラムンベース)系
お次のDrum’n’Bass、このジャンルの認識って実際どれくらいなんでしょうか?
「何となく聴いたことある気がする」という人ならそこそこ居ると思ってはいますが…
ドラムンベース(略:D’n’BまたはDNB)は、ドラムのリズムがつんのめってちょっと大人びたビートの電子音楽です。
典型的な(気がする)例がこちら。
サムネ、中指伏せてたんだ…w(貼って気づいた奴)
こちらのドラムに注目してください。
大部分においてキックとスネアで「ドッタン、ドタン」という、
3拍目と4拍目の間にキックが入っているのが分かるでしょうか?
これが最も分かりやすいDNBの特徴です。
この曲は2022年にリメイクがされていますが、リメイク前の方がDNBらしさが強いと思います。
こちらのリメイクではイントロなどで変化が強くついており、
特にイントロはハーフテンポで、むしろDubStep(ダブステップ)っぽくなっていますね。これもこれでカッコイイ!
また、こちらもDrum’n’Bassですね。
お洒落に病み切ってますなぁ~…ピアノが心地いい
こちらも同様の「ドッタン、ドタン」のリズムが繰り返されています。
ちょっと変化は多いかもしれませんがね。
え?もっと新しいやつ?ではこんな作品を…
r-906さん好きなので迷いましたがこちらで!
0:23から暫くは「ドッタン、ドタン」と「ドッタドッドタン」という、
ちょっとだけ変化の有るDNBリズムなんですが、
1:46で盛り上げた後(このBuildupで4つ打ちなのはよくあります)、
2:14からのリズム、お気づきでしょうか?
そう、完全に4つ打ちになってしまっています。
これは2020年代になってやってきた黒船、
4×4 Drum’n’Bass(フォーバイフォードラムンベース)と呼ばれるスタイルです。
本来成立しないはずのリズム同士を、曲中で強引に切り替えて変化を持たせたものですが、
「どう聞いてもドラムンベースではない」という事で相当な賛否両論があるようです。
ただr-906さんはこれを主要ジャンルとし、数多くの4×4 DNBボカロを制作されています。
DNB信者には申し訳ないけど、どれもかっこ良過ぎる…
さて一方で曲の大部分が4つ打ちで高速なスタイルも多いです。
それがお次のスタイル!(むしろこれ最初で良かったかもしれない)
Hardcore(ハードコア)・J-Core(J-コア)・高速4つ打ち系
電子音楽系ボカロ最後に挙げるのが、アップテンポな4つ打ちです。
むしろ電子系ならこれが主流なのかな?と思えるくらい、
大バズりした曲ってここに当てはまりがちな気がします。
まずはこちら!
ツミキさんの普段のスタイルはボカロックなどのバンドスタイルにも近いことがある印象ですが、
このフォニイに関してはかなりエレクトリックに思われます。
ピアノこそ目立ちますが、ドラム隊が機械的であったり、
イントロではEDMに多いボーカルチョップが入るなど、電子的なアプローチが多めに思えるんですよね。
また別の4つ打ちも聴いてみましょう。
このサイトで擦り続けているオーバーライドです。
この歌は更に4つ打ち率が極端に高く、ほとんど同じリズムで別の楽器の抜き差し、変化で曲展開を作っている印象です。
またこちらに至っては低めのピアノっぽい音以外はかなり電子音が多いので、
より電子音楽っぽさが強いですね。
このちょっと軽い感じやピッチエンベロープがさほどない感じは生ドラムでも有り得そうな気がして…どうでしょう?
また、ちょっとだけこれらよりは遅い例も。
若干BPMが遅い他リズムの変化も多いですが、
イントロやサビでシンプルな4つ打ちになるのがやはり分かりやすい見せ場ですね。
音色面ではかなり色んな音があって分かりにくいですが、
ピノキオピーさんらしくやっぱり電子音は多めですね。
雑記:これら高速4つ打ちの扱い
さて、これら早めの4つ打ちを挙げてきましたが、僕はこれらの定義を結構迷っています。
電子音楽には、大体BPM165か170以上当たりの4つ打ちとして、
”Hardcore Techno”(ハードコアテクノ)略して”Hardcore”がありますが、
果たしてこれらの4つ打ちボカロがHardcoreと呼べるかというとかなり微妙…。
本来ならもっと強力にキックが強調されたものがHardcoreの基本なのですが、
そこまでHardcoreらしく作られたボカロは多くなく、
かといってTechno・Tranceに分類するのもなぁ…という感じです。
そのため僕は、どんなスタイルでも「日本っぽい」だけですべて解決できてしまう(気がする)
”J-Core”的なボカロとしてまとめるのもありなんだろうか…と思っています。
或いは”ボカロCore”?少なくとも「速い電子音楽≒〇〇Core」という風潮はあるので、
一応意味として矛盾はないのかなぁ…と思います。
これぐらい「どうあがいてもHardcore」していれば分かりやすいんですが。
ハイブリッド・変則系
さて、ここまでで散々「こんなんでええんか」みたいな分類をしてきましたが、
それでも分けきれない問題児的神曲があるのがボカロなんですよねぇ…
まとめ
ということで今回は、様々なボカロ曲のジャンル・スタイルについて、
僕なりの見解をまとめてみました。
ここはかなり意見が割れやすい所であり、音楽ジャンルに詳しい方には違和感を与えてしまった方も多いかもしれません…
また、特にジャンルを気にしてこなかった方に注意していただきたいのは、
これらは非常に分けるのが難しいため、今回の説明はどうか真に受けず、
むしろ疑いの目も持ちつつ色々聴いてもらえるとありがたいです。
それでは、オヤカマッサン!