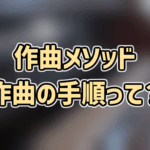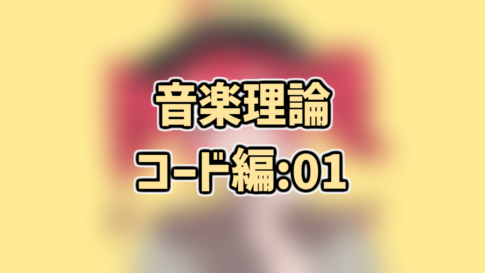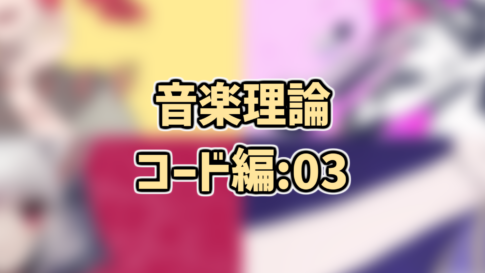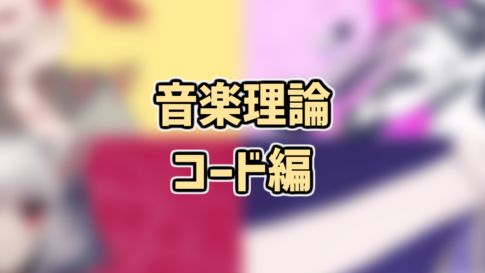皆さんごきげんよう。IWOLIです。
ボカロ曲で学ぶ音楽理論シリーズ
04となります今回は、前回学んだコードの役割をもとに、
実際のコード進行がどのように作られているか詳しく暴いちゃいましょう!
これを学ぶことで「何故このコード進行がイイカンジに聴こえるか」が分かり、
遂に、コードを自在に使いこなす段階の入り口に立てます!
長い…長かった…!
作曲の骨たるコード進行、ここを攻略すれば作曲できる未来は目前です!
頑張っていきましょう!
Contents
3つの役割とコード進行
まずは前回のおさらいも兼ねつつ、
トニック・ドミナント・サブドミナントの各役割たちが
どのように組み合わされてコード進行が作られるかを解説します。
各役割と次に向かいやすいコード
トニック、ドミナント、サブドミナント。
これらの役割は大まかに言って以下のような感じでしたね。
- トニック:安定→終わりに使いやすい
- ドミナント:一番不安定→展開を作れる
- サブドミナント:ちょっと不安定→バリエーションを持たせる
そして特に特徴的なのがドミナントです。
このコードはダイアトニックコードの中で特に不安定なため、
何としても安定したコードであるトニックに向かいたくなります。
その中で 「Ⅴ度-Ⅰ度」 という流れは更に強い力を持つため、
ドミナントモーションという名前があるんでした。
ツーファイブが強い理由
実はこのドミナントモーションの、5度上から降りてくる動きは、
Ⅴ(D)→Ⅰ(T) に限らず色んな場所で発生させられます。
そのいい例なのが前回も解説したツーファイブです。
Ⅱm(SD) – Ⅴ(D) – Ⅰ(T)
前回はあくまで、(SD) – (D) – (T)という
サブドミナントはドミナントへ、ドミナントはトニックへという流れと、
Ⅴ-Ⅰというドミナントモーションの解説に留めていましたが、
ここでⅡm – Ⅴの動きを見てみましょう。
一見するとⅡからⅤなので、「2,3,4,5」と4度上になります。
度数表記は基準となる音を「1度」と数え、そこから「2度」「3度」と数えていますよね。
相変わらず音楽理論が初見殺しな理由全開ですが、
度数で話している時は基準から1,2,と数えるのに馴染んでいると、この後が楽になるでしょう。
そして更にややこしい話が続きますが…
思い出してください、音楽は1オクターブの音がループしていますよね?
つまり、Ⅱ-Ⅴは1オクターブ上のⅡから降りてきているとも解釈できるんです。
この解釈で数えてみると?
「5,6,7,1,2」 そう、5度上ですね!
つまりツーファイブ Ⅱm(SD) – Ⅴ(D) – Ⅰ(T) とは、
Ⅱ-Ⅴ も Ⅴ-Ⅰ も、5度上からの進行なんです。
あくまでサブドミナントなので、
Ⅱm-Ⅴ の部分はドミナントモーションではありません。
ドミナントモーションだけではないとはいえ、
この5度下へ進む動きを続けているため、
ツーファイブは何とも言えない心地いい動きになっているんですね。
当然これもオクターブ上から見れば別の解釈が出来ます。
Ⅰ-Ⅴなら逆にⅤ-Ⅰですので、「5,6,7,1」と4つになります。
つまり「5度下がる進行」とは「4度上がる進行」と解釈する事もできますね。
今覚える必要は全くないですが、こういった一捻りした解釈が今後生きる事もあるので頭の片隅にどうぞ。
5度下じゃなくたって良い・コードの良い流れ
とはいえもちろん、
コード進行は常に5度下に下がるなんて言う法則はありません。
Ⅳ(SD) – Ⅴ(D) – Ⅵm(T)
このように上がっていっても良いですし、
Ⅵm(T) – Ⅳ(SD) – Ⅴ(D) – Ⅰ(T)
上下に動いたって大丈夫。
ただし、なんでもいいとは限らないのがややこしいんですね。
主に以下のような傾向があります。
- Ⅲmとドミナントは流れの中間に入れる(最初や最後に入れない)
- 同じ役割同士で代理コード→スリーコードの順にはしない
- ドミナントの次はトニック
これらを破るやり方はよく「コード進行の禁則」と言われます。
禁則をしてしまうと変な響きや流れになってしまいがちなので、
例えば「サブドミナントを使ったらドミナントに繋ぐ」
「ドミナントの次はトニック」という具合で、
パズルや頭脳ゲームの様にコードを組み立ててみましょう。
禁則とはあくまで変になりやすい傾向にある程度でしかないです。
色んなコード進行を見てみよう!
ここまででコードの流れや、
どういう風に進行を作ればきれいになりやすいかを学んできましたが、
「具体的にどんな進行にしたらいいか取っ掛かりがつかめない!」
という方も多いでしょう。
そこでここからは、音楽の様々な場面で使われる、
コード進行の定番パターンを幾つか紹介しつつ、
含まれるコードの役割・機能についても解説していきます!
※これ以降、ローマ数字だけだと見分け辛いかもしれないので、
所謂普通の「1,2,3」を併用します。
よくあるコード進行を使う事について、
「誰かが使ったものを使っていいのか?」といった、
いわばパクりを恐れる様な意見が出る事もあります。
単刀直入に言えば、何も問題ありません。
コード進行とは言わば「起承転結」の雛型であるとか、
「Aメロ-Bメロ-サビ」という曲展開、
或いは絵を描いたり写真を撮ったりする時の構図、
またはポーズの様なものと思ってもらって良いでしょう。
ピースのポーズをしているイラストや写真を出したとして、
「ピースをパクったな!」と文句を言われる事はほぼ有り得ませんよね?
米津玄師さんの「ピースサイン」(固有名詞)パクリだともちろんマズいですが。
コード進行に著作権はありません。(存在する事もあるかもしれないけど)
良いと思った進行はガンガン使っちゃいましょう。
というか誰も気にせず使い倒してます。
後述するⅣ-Ⅲm-Ⅵmなんて今や、無い曲を探す方が苦労するんじゃないですかね…。
Ⅳ-Ⅴ-Ⅲm-Ⅵm
まずはやはりこれ、「王道進行」という通称でも呼ばれる、
Ⅳ-Ⅴ-Ⅲm-Ⅵm という進行です。
Cメジャーキーだと、
F – G – Em – Am となります。
Ⅳ-Ⅴ-Ⅲm-Ⅵm
役割で言うと、
SD – D – T – T ですね。
ドミナントの次がトニックの代理コードになっている事、
Em – Am に掛けてマイナーコードで5度下がる進行、
そして、前半はメジャー、後半はマイナーという構成から、
全体の印象では暗めでしょうか?
暗すぎはしないけど明るいとは言えないような進行と言えます。
王道と言われるのは、この進行がJ-POPでは頻繁に見られる傾向があったことから。
かつてはJ-POPを席巻したと言っても良いでしょう。
最近では後述する 4 – 3m – 6m に似たコード進行の方が抜擢されがちなようですが、
特にYOASOBIさんはこの進行を好んでどこかに差し込みがちなようです。
怪物:サビが 4-5-3m-6m 主体になっている。
Ⅳ-Ⅴ-Ⅵm-Ⅰ
お次は Ⅳ-Ⅴ-Ⅵm-Ⅰ 、
先の 4-5-3m-6m と似ているためこれの派生とみなすこともできますが、
この形に当てはまる曲も多いためここで紹介します。
Cメジャーキーだと、F – G – Am – C ですね。
Ⅳ-Ⅴ-Ⅵm-Ⅰ
さっきの 4 – 5 – 3 m- 6m に比べ 4 – 5 – 6m – 1 は、
純粋に上がっていくスムーズながらちょっと暗い部分と、
6mから1のダイナミックにメジャーへ持っていく部分が印象的ですね。
また6mはマイナーキーの終わりに使える(マイナーで考えればⅠ度に当たる)ので、
最後の1を省いた 4 – 5 – 6m というのもアリです。
Ⅳ-Ⅴ-Ⅵm
後半部分にコードの変化が無くなるため、退屈になってしまう恐れもありますが、
逆に大きな変化を持たせたくない場合などに重宝します。
有名どころで言うと千本桜のイントロ(ターラータラララの部分)がこの 4 – 5 – 6m です。
またボカロ・J-POPでは無いのですが、
東方projectの生みの親であるZUNさんはこの 4 – 5 – 6m を
これでもかというほど連発し名曲を山の様に生み出すことから、
東方界隈では 4 – 5 – 6m を「ZUN進行」と呼んだりします。
これはマイナーキー基準で書いた場合であり、
これをメジャーに置き換えればⅣ-Ⅴ-Ⅵmになります。
またボカロ以外繋がり(?)で紹介しますと、
米津玄師さんのピースサインのサビでは、
最後に1に解決する、 4 – 5 – 6m – 1 がメインで使われています。
ただこの曲は結構な頻度でイレギュラーなコード、
ノンダイアトニックコードを使っているので、
4 – 5 – 6m – 1 だけでは説明できません。
ややこしいのでそこは別の機会で!
Ⅳ-Ⅲm-Ⅵm-〇
お次の Ⅳ-Ⅲm-Ⅵm-〇
これも 4-5-3m-6m の派生とみなせるかもしれませんが…
結構重要な進行なのでここで解説します。
こちらは先の補足がちょっと多めに必要かもしれません。
まず、何故最後が「〇」になっているからというと、
ここは色んなコードが当てはまる可能性があり、
或いはそのままⅥmを続けても良いからです。
別に「丸サ」という通称とは関係ない。
6を続ければCメジャーキーなら、F – Em – Am です。
Ⅳ-Ⅲm-Ⅵm
そして、この進行のキーとなる 4-3m-6m という並びを見て、
コード進行にある程度明るい方は「丸サ進行」というワードを思い出されるかもしれません。
これは椎名林檎さんの名曲「丸の内サディスティック」に由来します。
同じ進行が存在した更に古い曲から、
Just the Two of Us進行という呼び名もあります。
ただこれは2つ目のコードをⅢmではなく、
別のノンダイアトニックコードに置き換えている事が重要だと思いますので、
今回は 4-3m-6m を丸サ進行とは呼びません。
丸サと呼ぶ人も居るかもしれませんが…そうですね僕が敢えて言うなら、
「丸サ未満」ですかね?(ダサ過ぎる…)
とはいえこの丸サではない進行もとてもよく見かけます。
真の丸サ進行も含めると最早至る所で見るというほどになりますね…。
例えばフォニイなんてなんと、
曲全体に渡ってこの 4-3m-6m の派生系を連発しています。
Aメロだけがダイアトニックコードのみで構成された 4-3m-6m で、
Bメロ-サビは丸サの派生と言えるノンダイアトニックコードを使ったものになっています。
また(これはノンダイアトニックコードを含む方ですが)
フォニイとはまたちょっと違った変則性を持つのがKINGのサビですね。
この進行の基本的な1ループを数字で表すと、
6m-1-4-3 となります。(多分一番後ろは“3m”ではなく“3”のはず…間違ってたらすみません!)
これだけを見ると6m始まりで全然違うように見えますが、
これはループしています。つまり、
6m-1-4-3-6m となるわけです。
こういったループで考えると同じ進行になるという事もよくあります。
Ⅵm-Ⅳ-Ⅴ-Ⅰ
こちらはこれまでと違い、
Ⅵ度から始まる進行です。
6m – 4 – 5 – 1 進行、小室哲哉氏が好んで使ったことで有名な、
通称小室進行です。
Cメジャーキーだと、Am – F – G – C になります。
Ⅵm-Ⅳ-Ⅴ-Ⅰ
学校のチャイムと同じ並びですね。
最初だけは6mで暗めなのですが、
メジャーが続く上に最後が1度で終わるため最終的には結構明るい雰囲気に解決します。
代表例はやはり…オーバーライドが真っ先に思い浮かびますね。
うわっ私のサイト、オーバーライド擦り過ぎ?
流石に芸がないので別の例を紹介すると、
実は千本桜のサビがこの小室進行をメインにしています。
千本桜についてはメロディ的にもコードの終わり方もマイナー寄りと解釈した方がしっくりきそうですが、
それでも小室進行がメインなので明るく聴こえる傾向にあると言えるでしょう。
サビの大部分が小室進行な千本桜ですが、
最後だけ先に出てきた 4 – 5 – 6m を引き延ばしたものが来ます。
メロディがマイナーで終わるのでこっちの方が終わりとしてしっくりきますね。
これが最後まで小室進行(6-4-5-1)だと凄く中途半端になってしまいます…
これはひどい
Ⅰ-Ⅴ-Ⅵm-Ⅳとループの起点
最後に紹介するのはこちら、
Ⅰ-Ⅴ-Ⅵm-Ⅳ 通称ポップパンク進行と呼ばれるものです。
Cメジャーキーだと、C – G – Am – F となります。
Ⅰ-Ⅴ-Ⅵm-Ⅳ
今度はチャイムの後半部分ですね。
ここも「キンコンカンコン」と言う派と、ここは「コンキンカンコン」と呼ぶ派が居ましたねぇ…
こちらはちょっと明るすぎる為か、
現段階でボカロ曲やネットで流行した曲での使用例は把握していませんが、
「アナ雪」の“Let it Go”がこれらしいです。
海外の映画ってタイトルが短くてスタイリッシュですよね。
何故これを紹介したかというとこのコード進行の特徴として、
Ⅴ度以外のどこを起点としても、ループとして成立するという点があるからです。
先ほどのKINGの 6m-1-4-3-6m 様に、
- 1 – 5 – 6m – 4
- 6m – 4 – 1 – 5
- 4 – 1 – 5 – 6m
というパターンへの派生が考えられます。
これだけでもまた違った聴こえ方をするから面白いですよね。
次の小節頭でトニック(1度や6度)に持っていかないと凄く中途半端な終わり方になってしまいますので注意です。
それはもうさっきの小室進行化の所為でオチが無くなった千本桜以上にオチが無くなってしまうので…
そのキーにおける不安定担当とあって不安定過ぎて最初には向きません。
Ⅶm(♭5)はもっと向かないでしょう。
まとめ
以上、コード進行の構造や流れ、
またよく使われるコード進行について解説しました。
お疲れ様でした!
コード進行って凄くややこしいですよね…
順を追って説明してきたつもりではありますが、
段々と付いていけない所もあったかもしれません。
そんな時は振り返ってみたり、試しに好きな曲の楽譜やピアノロール、MIDIを見てみたりしてみてください。
これを読むあなたにとって、少しでも作曲のハードルが下がったら幸いです。
一方で今回はスケール外の音を用いない、
ダイアトニックコードのみを使って解説しましたが、
残念ながらこれだけだとリスナーの注意や好感を惹けるような効果的な曲にはし辛いのが事実です。
多くの有名曲たちは色んな所でこの定石と言えるダイアトニックスケールからはみ出すことで、
耳を惹くような個性を出しています。
とはいえここは結構ややこしいので追々解説するとして、
そろそろ何か作って見たくないですか?
という事でお待たせしました!(?)
次回からは実際にゼロから作曲していくための、
具体的な作曲メソッドについて解説します!!!
お楽しみに~!