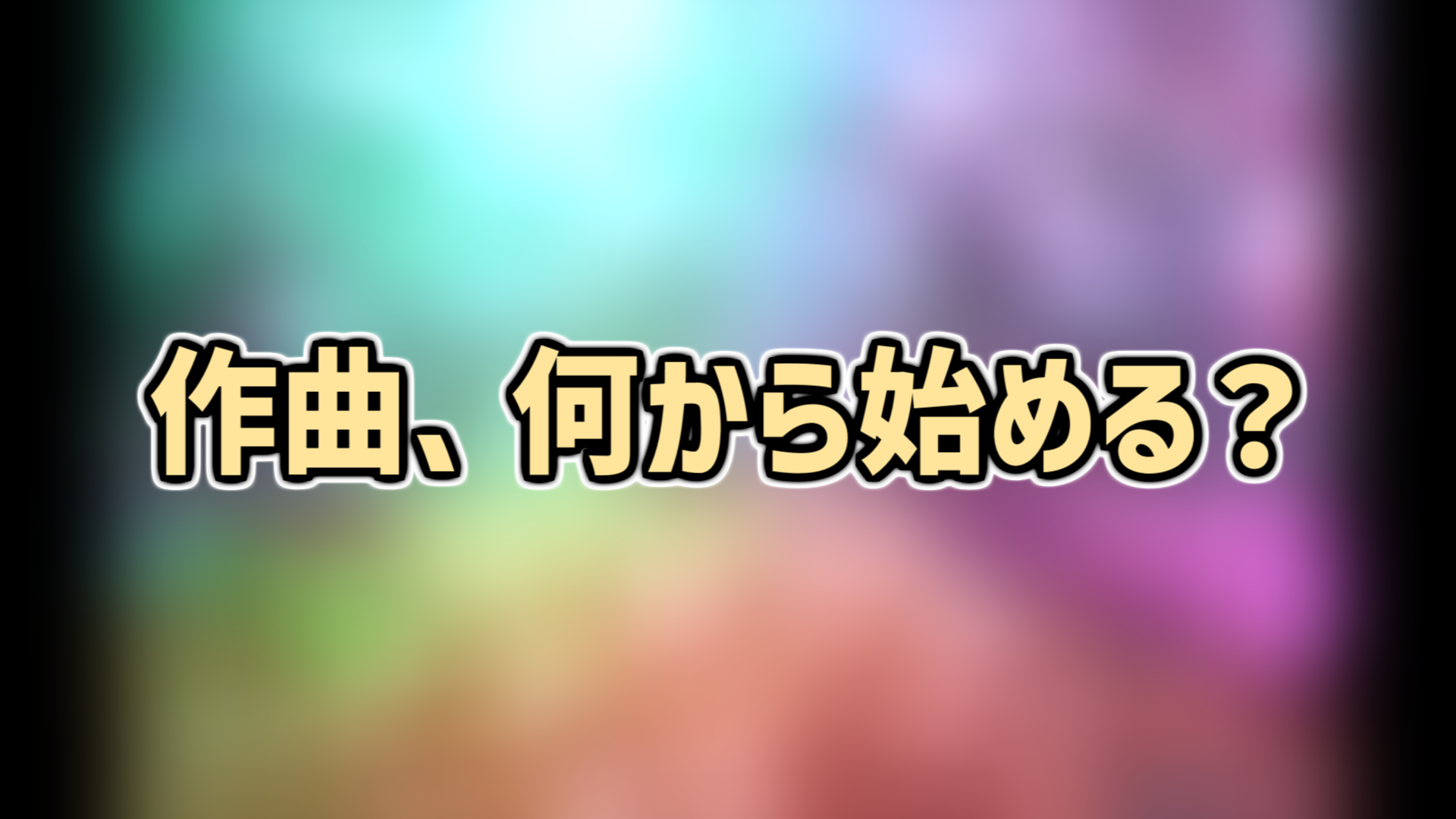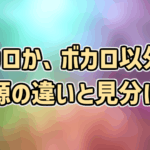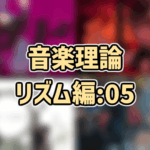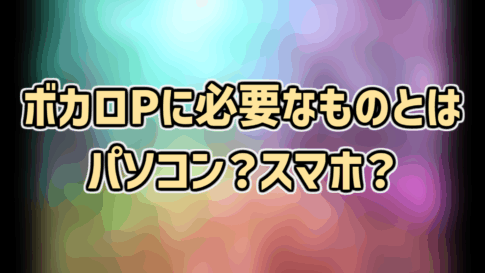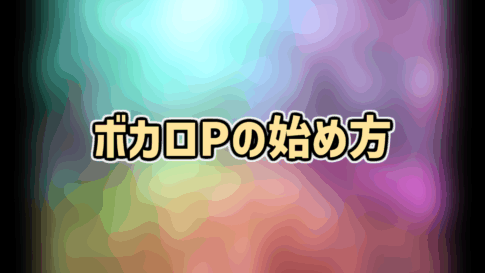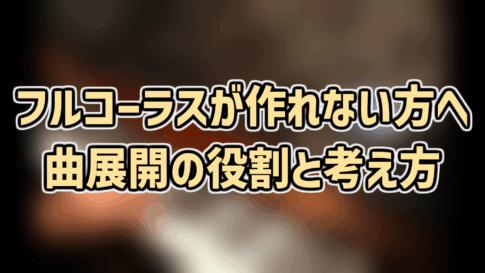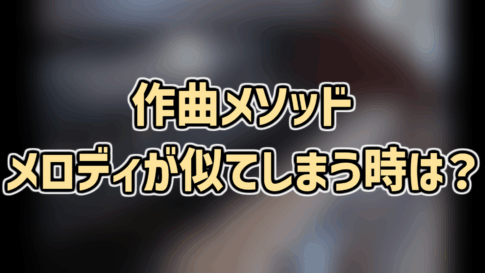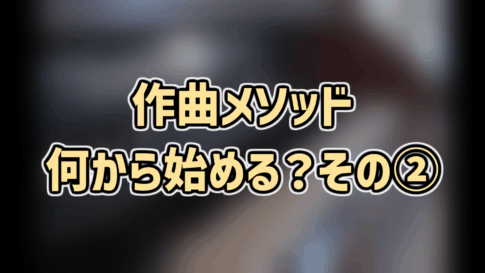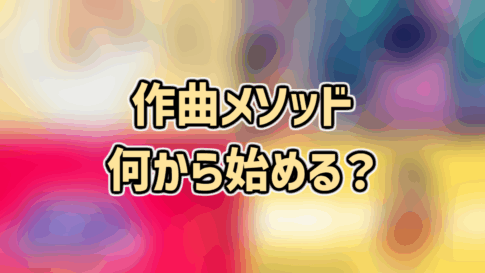「私は喉から…」「私は熱から…」ではありません^^;
どうも皆さんごきげんよう。駆け出しボカロPのIWOLIです。
「作曲を何処から始めるか?」何かと難しい問題だと思います。
まず作った事が無い方にとっては、何処から手を付ければ良いのか途方に暮れてしまうでしょうし、
曲を作った事のある方でも、最初の一歩をどう踏み出すかが難しい方も多いのではないでしょうか?
今回はそんなお悩みへのアプローチとして、
「作曲第一歩の踏み出しパターン」と、それぞれの長所・短所を解説します!
自分で作る時のヒントにしてみてくださいね。
メロディ
まず一つ目は王道と言える一手、メロディです。
何もない所から、真っ先にメロディを考えて、
そこからコードや歌詞、曲展開などへ発展させていくパターンですね。
「メロディを先に作る」ところから、「メロ先」と言われたりもします。
これを想像する人は結構多く、また同時に、
「これが出来ないから私は作曲が出来ない…」と思っている人も多いかもしれません。(僕がそうでした)
この方法のメリットは何と言っても、
- 印象的なメロディを自由に作れる
というのがあるでしょう。
一方でやはり大きな問題点として、メロディを作る前と後で、
- 前:そもそも作れない・メロを閃く前提の解説が多い
- 後:メロディにコードが合わせられない
という状態に陥る可能性がある事が挙げられると思います。
順番に解説していきますね。
メリット:自由に作れる
自由にメロディを作れるのは重要なメリットの一つでしょう。
コードや歌詞、キー、音域などといった他の縛りが無い中で考えられるため、
のびのびとメロディを組み立てられるでしょう。
そもそもパッとメロディが浮かんだり降りてくるタイプの方にとっては、
むしろ「メロディ以外から作る方がしんどい」という事にもなるんでしょうね。
デメリット①:自由過ぎて作れない
とは言えどデメリットも背反で、それは、
自由度が高過ぎてメロディを作る取っ掛かりが無いという物。
「自由に作れるからと、試しに作ってみたら、
なんか何にも成れないゴミばっかり生まれた…」
そんな経験、ありませんか?
テーマを「何でもいい」と言われたり、「好きに作ってみて」と言われた方が、
逆に困ってしまう事、あると思います。
メロディにおいてそうなってしまうタイプの人にとっては、
メロ先という手順はむしろ悪手以外の何物でもなくなってしまうでしょう…
デメリット②:コードが合わせられない
更にもう一つのデメリット、コードが合わせられなくなるというのも考えられます。
「まだコードの話は出てないじゃん?」と思ってしまいますが、
そうして取り敢えず苦戦しながらメロディを考えた後に気づくことがあります。
「どんなコードを合わせても変に聴こえる…」
原因はメロディラインとコードの構成音的な相性が悪いこと。
後先を考えずに作ってしまったために、
メロディとコードの間で不協和音が生まれてしまうというのは、意外と珍しくないと思います。
そしてそれを取り除くとするとコード進行が変になるか、
折角考えたメロディにまたテコ入れをしたりと二度手間になる可能性が出てきます。
コード
二つ目はそんなメロ先の欠点を解決する方法、コードです。
コード進行を先に考えた上で、メロディ、歌詞、編曲などに移っていく手法ですね。
一見難しく感じるかもしれませんが、主に
- コードをメロディ作りのヒントに出来る
- 着実に制作していきやすい
- コード進行・メロディとの相性が良くなる
といったメリットが挙げられます。
一方デメリットとして、
- コードの知識が無いとコード進行がちぐはぐになる
- 自由なメロディが作りにくい可能性がある
- 良くも悪くも「普通過ぎる」曲になるリスクがある
というのもあげられるでしょう。
順番に解説していきます。
メリット①:メロディ作りのヒントに出来る
1つ目にして最大のメリットは、コードをメロディ作りのヒントに出来ることです。
さっきの「メロ先」だと、メロディが最初に思いつかない人にはお手上げ感があると思います。
ですが、先にコード進行さえあれば、その構成音を元にメロディを組み立てて行くことが可能になります。
メリット②:着実に制作しやすい
2つ目は1つ目の延長に近いですが、着実に作曲がしやすくなります。
メロ先だと直感的に作る人も多くなってくると思いますが、
良いメロディが浮かぶまで博打を打つような感じになってしまいます。
コード先の場合は、コードもメロディもかなり理屈で組み上げていくことができるので、
一音ずつパズルのピースを嵌め込むように一歩ずつ前進する作曲が出来るようになります。
メリット③:構成の相性が良くなる
3つ目は、1・2を合わせることで必然的に生まれるメリット、
曲を構成する全ての相性が良くなるというものです。
考えてみれば当然ですが、出来上がったコード進行に噛み合うように作曲していくため、
メロディとコードが合わない、曲展開に説得力がなく、違和感を覚えるといった、
全体で見た時の不整合は起きにくくなりますね。
デメリット①:コードの知識が必須
一方のデメリット1つ目は何と言っても知識問題です。
これを見ている方で、音楽理論に自信のある方はどれくらいいらっしゃいますか?
…正直僕だって自信はないです。結構最低限かなと思いますね。
もっと理論面が未熟でコードの事が何もわからない場合、
「そのコード進行がどうにもならないんだが!!!?」と言いたくなるでしょう…
作曲の前に予習が必要になってくるのはやはりデメリットと言えるでしょう。
残念ながら、「勉強が要る」というのは理論の本懐と言わざるを得なさそうです。
閃きや偶然だけで良いものが出来上がる天才たちに対して、
そういったものを持たない人でも「努力で補える」ためのツールが理論だと僕は思っていて、
そう考えると、「(勉強さえすれば)命中率100%になる」みたいな、
無いものをカバーする代償というのも納得かなと思います。
デメリット②:自由なメロディが作りにくい
2つ目として自由にメロディを作る事は出来なくなってくるというのがあります。
ここはしゃーなしですが、コードに合う事を最優先でメロディを作っていくため、
メロ先の様な自由度では作曲出来なくなってきます。
この方法はメロディだけでなく、全体を計画的に作るための方法と言えるので、
逆にめっちゃ良いメロディのためにコードを付ける様なやり方には向いていないでしょう。
デメリット③:「普通過ぎる」曲になる
そして2つ目のデメリットがある故に起こるのが3つ目、
普通過ぎる曲になってしまう可能性があるということです。
これは結構痛手に感じる人が多いかもしれませんが、
やっぱりメロディに強めの制約を掛けて作っていくので、
凝ったコード進行や攻めたメロディを意図的に作れるようにならない限りは、
どこか一辺倒になってしまう可能性があります。
J-POPなどでいうAメロ・Bメロに使うのが良いと考えています。
詳しく知りたい人に…
この方法はデメリットこそあれど、再現性があり、
達成感に繋がりやすいことから結構お勧めしています。
詳細を以下で解説していますので見てみてくださいね!
①「そもそもコードが分かんない!」という方に
②「コードはわかった!」という方に、もっと詳しく教えます!
「その①ってじゃあ何なの?」その答えは最後にお伝えします!
アレンジ(編曲)
3つ目の始め方としてちょっと異色ですが、
アレンジ(編曲)から始めるという戦略をご紹介します。
「曲も無いのにいきなりどうやって編曲するの?」と思うかもですが、
実はこの方法も意外と使えます。
特に楽曲の編曲面を意識しがちな人、ジャンル感やリズム感など、
曲の雰囲気を重視して好む人にオススメです。
また、ジャンルによってはメロディ・コードなどの要素が弱く、
最初から最後まで大部分が編曲によって形作られるようなサウンドもあります。
そのメリットとしては
- あらかじめ曲の雰囲気をコントロールできる
- 最終的な雰囲気のイメージが作曲の取っ掛かりになる
- いきなり雰囲気が出てテンションが上がる
などがあるでしょう。
一方のデメリットは、
- 編曲の知識がジャンル・楽器の数だけ必要になる
- 曲展開においてコード先以上に退屈になる恐れがある
辺りでしょうか。
メリット①:曲の雰囲気をコントロール
まずメリット1つ目は何と言っても、曲の雰囲気を真っ先に決められること。
イケイケアップテンポな曲にしたいのか?
ふわ~っと流れる様な曲が良いのか?などなど、
こういった雰囲気は、作曲ではなく編曲によって大きく変わる事が多いです。
例えばテンポも決めずにメロディやコードを決めても、
そこからBPMを10上げただけでも、意外と雰囲気はガラッと変わるものです。
他にもメインとなるリズムパターンや土台の楽器構成を決めておくと、
次のステップに進みやすくなるという事があります。
メリット②:最終的なイメージが取っ掛かりになる
そしてそんな次のメリットが、編曲で最終的なイメージを先に作る事で、
作曲していく取っ掛かりになるということ。
特に曲の楽器構成に意識が行くタイプの人は、
ドラムやベースなどの土台が変わるだけで見違えた印象を人一倍強く受けるでしょう。
ピアノでベタ打ちコードとメロディだけだと、
例えこれから良い曲になる素材であってもショボく見えてしまう事ってありませんか?
これは人による所もありますが、そんな問題を先に潰しておけるというのも大きなメリットです。
当然ですがピアノソロがショボくなるなんて言う事は言いません。
ま〇しぃさん大好きです。
ですがそういった演奏は、演奏時の強弱やコードの鳴らし方、
メロディと伴奏の掛け合いなどでとにかく表現に趣向を凝らしています。
つまり、ピアノだけで編曲まで完成させているんです。
逆に言えば、ただのベタ打ちは編曲されていないピアノという事になり、
これだとショボくなる可能性が高いよということなんです。
メリット③:テンションが上がる
そしてこれは更に人によるというか感情的なメリットですが、
単純にテンションが上がるということもあります。
さっきも補足した通り、ただの作りかけみたいなピアノだけ演奏でも、
ちゃんと演奏などで編曲がされているだけで、感情に訴えかける様な作品に仕上がりますよね?
論理的な理由では無いですがこれはとても大事。
音楽そのものが、作り手の感情を乗せ、聴き手に訴えかける物である以上、
作品を無感情に作るというのは不自然ですよね?
ですが、機械的に作っていき、機械的な演奏ばかり聴いているとそんな感情が薄れ、
「結局何が作りたいんだっけ…」となりかねません。あるよね…作ってる最中に冷める現象…
それを解決する一つの方法として挙げられるのが、
先に編曲を済ませよう、ということなんです。
デメリット①:知識がジャンル・楽器の数だけ必要
デメリットとして挙げられるのはやっぱり知識の問題、
ちゃんとその編曲をする為のノウハウが無いと、結局まともな「編曲先」が出来ないというのがあるでしょう。
更にコード進行とは違い、編曲は方向性の数だけ全く異なる知識が必要で、
応用の聴かなさからより事前準備が必要になってきます。
デメリット②:コード先以上に退屈になる恐れがある
またもう1つのデメリットとして、コードを先に作る時以上に退屈になる恐れもあるでしょう。
例えば先ほどの知識的な問題があり、「自分はロックっぽいのしか使えない」という場合、
新たな知識を蓄えない事にはずっと同じようなものを作ってしまうでしょう。
後から編曲するなら修正しやすかったかもしれない所を、
先に編曲していたせいでそこを崩すのがコワイと思ってしまう可能性もあります。
またこれはEDMなどで特に注意が必要ですが、
ジャンルによっては曲の構成や展開が概ね決まっている場合も多くあります。
それ自体は何も問題ないのですが、あまり編曲先に傾倒し過ぎると、
このジャンル特有のお決まりから抜け出せなくなるというのも考えられますね。
作詞は?
さてここまで読んでいて「あれ?作詞から先は無いの?」と思われたかもしれません。
正直言って僕はこの方法、現代だとあまり推奨しないかな…と思っています。
何故なら、作りにくいからです。(直球)
良し悪しを整理すると、メリットは
- 歌詞最優先な歌が作れる
デメリットは
- 歌詞が収まるメロディ作りに難航し、後が無くなる
という感じでしょうか。
とにかく強いメッセージを持つ人にとってはメリットが大きく映るでしょうが、
その引き換えになる代償がバカでかいという事を忘れてはいけません。
先ほど、ただでさえメロディは
「思いつかない&コードに合わない」という二重苦があったのに、
そこへ「歌詞が合わなければいけない」という制約がプラスされます。
つまりコードと歌詞で、ピッチ面とリズム面両方の縛りが課されます。
…どれほどの地獄が待っているかは自明ですね?
もちろんこの方式が活きる方向性というのもあります。
それは歌詞が主体となる作品を作る時です。
例えばしんみりと詩を聴かせるようなバラードや、
とにかく韻を踏んでノリノリなラップなどはありかもしれません。いやラップはビートが先か…
或いは、「ここだけは聴かせたい!」という歌詞だけ先に決めるのはアリです。
ただ先に全体の歌詞を決めてしまうと、後々苦労するかもよということです。
個人的なオススメ
最後に個人的なオススメの初手としてテーマ先というのを紹介します。
何なら僕はコード先よりももう1つ手前としてこのテーマ先を推しています。
そう、さっき言っていた「何から始める?」のその①です。
遂に音楽的な所でも歌詞でも無くなってしまいましたが、
これ、意外と色んな人が意識せずにやっているんじゃないでしょうか?
テーマ、即ち「何故この曲を作るのか」から決めるという作戦です。
実際に「こんな歌を作ろう!」というのを漠然と思いついているケースってきっと多いですよね。
一応メリットとデメリットを上げると、
メリット
- 曲を作る全ての工程において支えとなる軸が出来る
- 軸のお陰で迷いが減る
デメリット
- テーマが漠然としていると逆に作り辛くなり得る
- テーマ決めに難航する人には辛い…
- テーマだけが音楽の全てじゃない
という感じになるでしょうか…
いわば作品の根っこになる部分をどれだけ煮詰めるかという話なので、
全然音楽的な話にならないですが、心理的に作りやすいか否かという感じですね。
これも結構人による所が強いと思いますが、
今まで曲を作るのに苦労していたという方は一度試してみて欲しいです!
詳細はこちらから!
まとめ
という事で今回は、どうやって曲を作り始めるか?という事について、
幾つかのアプローチを紹介しました。
個人的な事を言っちゃうと、やはり「僕は大体コレ」というパターンが決まってくるのですが、
これはほとんどの人にとってそうだと思います。
メロディ・コード・歌詞・アレンジ・テーマ、
何処から作り始めても同等にハイレベルなものが必ず生み出せる人は相当稀有でしょう。
なので今回は敢えて、「色んな方法が考えられるよ!」というお話をしました。
今まで、何となく「メロディ作らなきゃな…」と考えて作曲を始めたりしていた方、
是非試しに最初の一手を変えてみてください!
ただ作曲のスムーズさやクオリティだけでなく、自分でも知らなかった自分に気づけるかもしれませんよ!
それでは、オヤカマッサン~