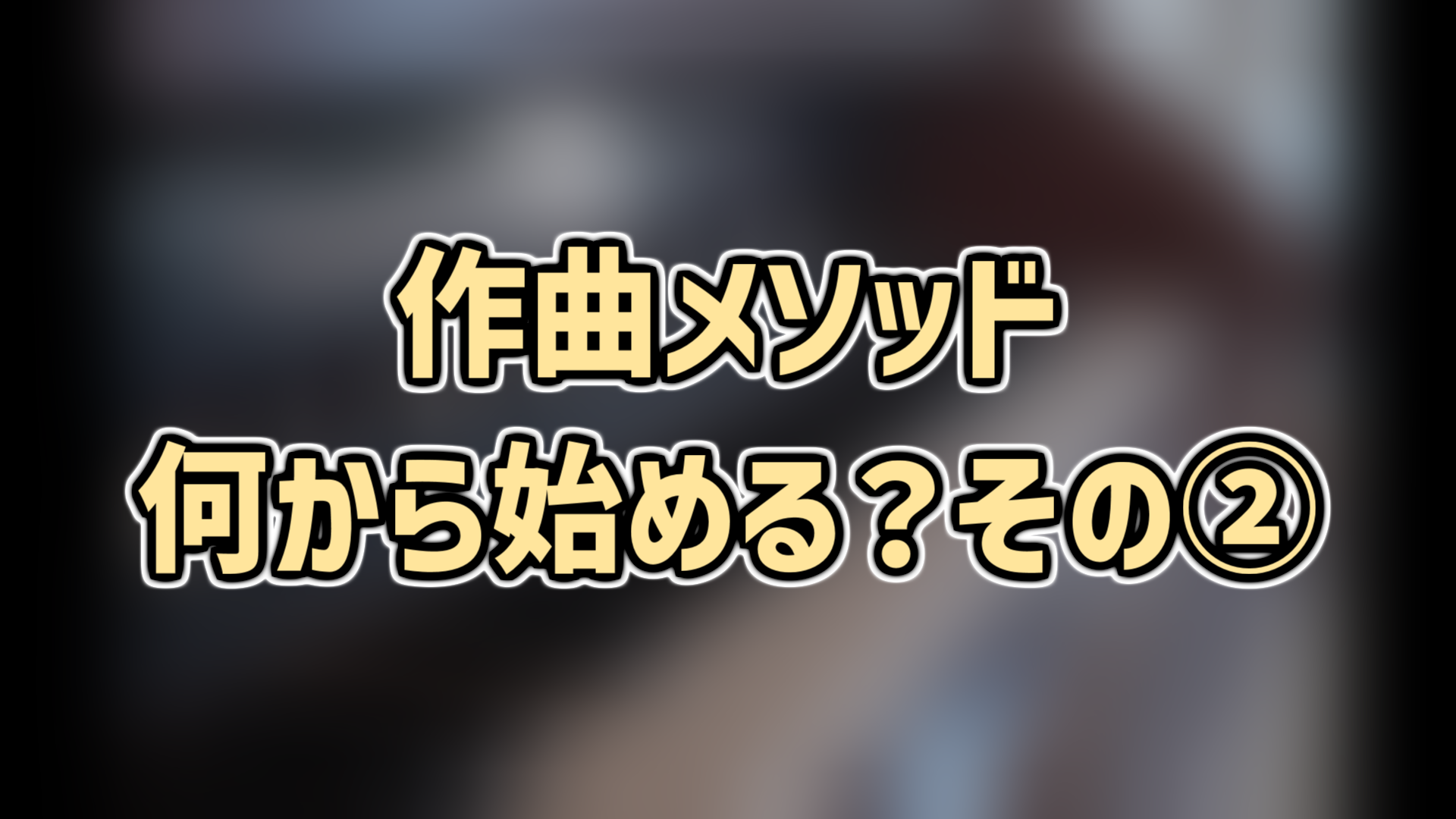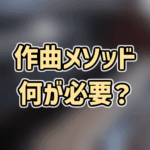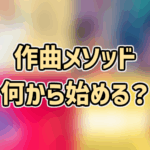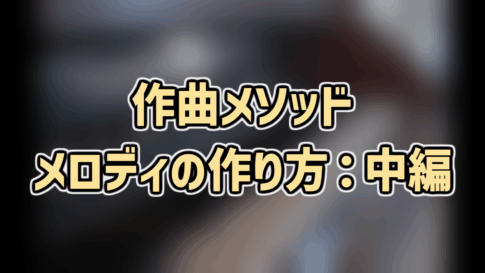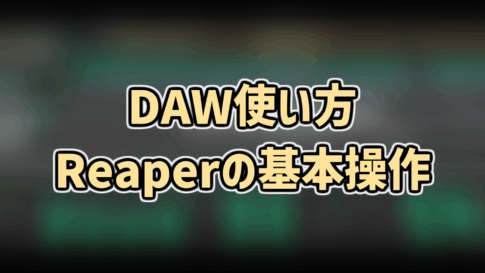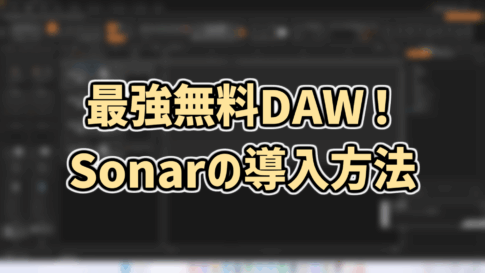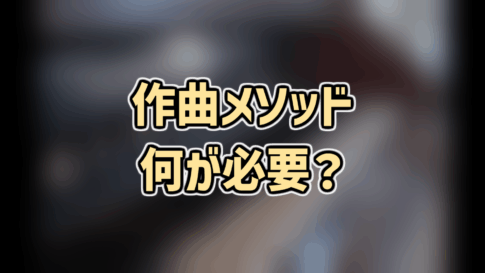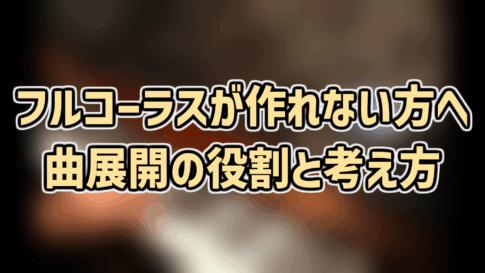皆さんごきげんよう。IWOLIです。
前回、作曲を始める時は初心者ほど、
「テーマ」から決めるとよい、という話をしました。
ですが、作曲の初期段階ではもう一つ先に決めておくとよい「〇ー〇」があります。
もう御察しかもしれませんが今回はそれについてお話しします!
Contents
やっぱり「コード」は大切
表題にありますが、この二つ目の「〇ー〇」の正体は「コード」です。やっぱり。
まあ前回でも「間違いではない」って言ったぐらいですからね。
この「コードから作る」というのは推奨する人も多いかな?と思います。
一方で、作曲の手順は幾つか考えられます。
J-POP・ボカロのような歌ものを作る上で、
歌詞・メロディ・コード を作るとした場合、そのままに
- 歌詞から作る
- メロディから作る
- コードから作る
という3パターンが考えられます。
それぞれにメリット・デメリットが考えられますが、
この中で僕はコードから作るパターンを推しています。
その理由が主に以下の通りです。
- コード進行は世界観・ストーリーを作る
- コード進行は縛りが大きい
- メロディの道しるべになる
- 作詞はメロディ以上に自由過ぎるので後!
一つずつ解説していきます!
コード進行は世界観・ストーリーを作る
まず一つ目の理由は、コード進行で世界観やストーリーを作れるから、というもの。
世界観やストーリー、そうつまりはテーマ!
これまでの講座で、コードとは異なる複数の音の重なりによって、
明るい・暗いなどの単音だけでは表せない空気感を表現できるものと解説しました。
そしてその単独のコードが表した空気感たちを繋ぎ合わせ、
コード進行となることで空気感の進行、ストーリーが生まれます。
コード進行が変われば与えるストーリーや世界観の印象も変わるわけですが、
前回で先に曲のテーマを決めていれば、
次にこのコード進行を決めることで楽曲を目標とするテーマにより近づけやすくなります!
もちろん他の要素でもテーマを表現していくわけですが、
コード進行は特に作品の骨や土台に近く、
また後から変更が効きにくい、もしくは変更すると別の部分に影響が出てしまう恐れがあるため、
コード先を推奨しています。
その具体的な理由はお次に!
コード進行は縛りが大きい
2つ目の理由はコード進行は「縛り」が大きいから、です。
過去のコード解説にて、
- コードには役割があるということ
- 役割によって好ましい進行があること
というのをお話しました。
コードにはその曲のスケールにおいて、
T(トニック)・D(ドミナント)・SD(サブドミナント)
の主に3種類の役割に分けられて、
基本的には
SD → D → T という流れがスムーズなんでしたね。
当てはまらなければ全部ダメというわけではないですが、
何も考えずテキトーに打ち込んだコード進行が、
「なんか変だな?パッとしない?」と思った場合、
これらの基本形から大きく逸れた、変な進行になっていることが多いです。
そう、コード進行って変になるリスクが高いんです。
もし、テキトーに打ってもそれっぽくなってしまう天才の方や(そんな人はここに来るのか?)、
それっぽくないかもしれないけどそのまま突破するなら問題ないですが、
自然な流れのコード進行を持った曲が作りたい場合、
先に自然なコード進行を固めてしまう、
または既存のコード進行をそのまま流用して作曲を始めた方が後々楽になるでしょう。
変になる可能性でいえばメロディ・歌詞も十分あるのですが、
コードとの大きな違いが代用の効きやすさです。
メロディの道しるべになる
ではそのメロディについて、何故代用しやすいか、何故道しるべになるか解説します。
代用が効く理由
メロディの場合、コードに比べて短い時間で次の音に移れます。
同じコードが変わらず鳴っている間、
メロディラインまでずっと変わらず同じ音ってことはまずないですよね?(というかそれじゃメロディも実質コードの一部である)
メロディは例えば8分音符や16分音符単位で違う音に移ることは頻繁にあります。
ですがコード進行はそんな高速で切り替えるわけにもいきません。
メロディは一瞬変な音が入っても、
すぐ別の音に切り替えればあまり問題になりません。
道しるべになる理由
二つ目が道しるべになるというもの。
メロディとコードの共通点はやはりなんといっても、
ピッチ(音高)の概念があるということ、これがリズム楽器や効果音との主な違いです。
こらそこ!ドラムもピッチあるとか揚げ足取らない!
そしてこれらは同時に鳴ることによって、何世紀も続く今の音楽の基本形、
ホモフォニーが形作られています。
つまりピッチを持った音同士が同時に発せられるということ。
これは言い換えると、メロディがコードの構成音のいずれかに対して、
半音違うピッチの音を奏でてしまった場合、
メロディとコードの間で不協和音となってしまいます。
こういったコードの構成音と不協和音でぶつかる音のことを、
アヴォイドノートと呼びます。
また、たとえアヴォイドノートでなくとも、コードに無い音をメロディが奏でた場合、
その音が鳴っている間だけ実質的に別のコードのような響きになります。
例:コードがGメジャーコード、メロディがファの場合
G:ソ・シ・レ + ファ
→G7:ソ・シ・レ・ファ っぽくなる
これを狙っているなら問題はないですが、
逆にコードでG7を鳴らさない理由が迷子になります。
こういった所で説得力を失ったり、
知らずに先ほどのアヴォイドノートを踏んでしまうリスクを減らせる手法が、
メロディの大部分をコードの構成音から取るというものです!
道しるべがある時ー!ない時…
コードによる道しるべがあるとメロディ作りは本当に簡単になります!
先に決めた、コード進行の好ましい流れによって、
曲の各部においてなっているコードが決まっているなら、
例えば3和音(トライアド)なら
その間鳴らすメロディ音の候補はたったの3つに絞られます。
逆にコードを先に決めなかった場合、メロディに使える音が絞り込めないだけでなく、
メロディの動きにコード由来の一体感が無くなりとっちらかる恐れもありますね。
そして何より、そうやってコードを考えずに生み出されたメロディにコードを付けようとした時、
- どうあがいてもアヴォイドノートが生まれてしまう
- 不自然なコード進行にしないと合わない
- 早過ぎるコードの移り変わりが必要になる
などの無理が生じ得ます。
これを解消しようとする場合、結局先に決めたメロディに手を入れ、
もう一度組みなおす二度手間になってしまうことでしょう…。
これまた僕の拙作、アナザーランドでも、
先にコード進行を決めていたくせに、
イントロのリフはコードガン無視でメロディを書きかけたのですが、
そうやって決めたメロディがコードに合っておらず微妙な雰囲気でした。
そこでコード構成音を意識した瞬間に一変!
最終的に採用することになるイイカンジのメロディが完成しました。
作詞はメロディ以上に自由過ぎるので後!
メロディはコードより自由度が高く代用しやすいと話しましたが、
歌詞の場合もっと自由度が高くなります。
何せ候補の数が違いますから。
メロディで使う音の種類はメジャースケールなら7つ。
イレギュラーな音を入れても12音律なら12個(またはオクターブ違い)となります。
コードについても、メジャーダイアトニックコードだけなら7つ。
ノンダイアトニックを入れてもクセのあるコードは使いづらく、
現実的に使用可能なコードは多くはないでしょう。
一方の歌詞は?
言葉の数なんて分厚い辞書になるくらい山ほどありますよね。
たとえ同じような意味を持つ単語に絞っても相当候補は挙げられ、
更に前後の言葉を変えて生まれるパターンも入れれば、
目標の表現一つでさえ無限の可能性が広がっています。
色んな方法があるのに歌詞から先に固め、
それに合わせ言葉よりも候補や自由度の狭いメロディやコードを決めるルートの方が難易度が高いのは想像に難くないでしょう。
そしてコード・メロディをもし修正した場合、
歌詞も修正する二度手間が必要になるのも同じです。
歌詞の場合ピッチはあまり気にしなくていいですが、
言葉本来のイントネーションを意識したり、
母音や子音の発音を音程の動きやリズムに嚙み合わせる工夫は、
有るか無いかで完成度がかなり変わってきます。
初心者のうちは完成度云々より完成させること自体を考えた方がいいとは思いますが、
それでもやはり作りやすさは、
コード>メロディ>歌詞
が一番楽ではないかなと思います。
よっぽど方向性の目標から、
この歌詞で絶対に表現したい。弄りたくない!
という理由でもなければ歌詞は最後が良いでしょう。
例外:コード進行が存在しない曲もあったりはする
ここまで「コード進行から作れ!」という話をしていてなんですが、
そんなコード進行がそもそも存在しない曲というのも実は割とあったりします。
歌詞が無いとかなら最後の手順がないだけですが、
コードがないってどう作りゃ良いんだよ!?
と思うでしょう…
ここで例をお聴きいただきましょう。
こんなNeuroFunkと呼ばれるドラムンベースの一種から、
こういったダーク寄りのPsychedelic Tranceというジャンルもそうですね。
またコードが全く動いてない訳では無いですが、
実はJ-POP寄りでもたま~にあるんですよ、コード進行の少ない歌が。
聴こえにくいかもですが、低音が一定か、二つの音を行き来するだけのシンプルな進行なのが分かるでしょうか?
そう、こんな感じの、
ベースラインがほぼ動かず同じルート音を鳴らし続けるようなスタイルですね。
EDMを中心とした電子音楽の世界では、
そもそもメロディやコード進行といった感傷的なテーマ・メッセージ性は端から無し、
キックと個性的なベース音でひたすら
重低音で踊れ!な楽曲が目白押しです。
こういったジャンルだと凝るべきなのはむしろシンセ・エフェクトなどによる音色づくりの方で、
コード・メロディについてはずっと一定で良いなんてことがよくあります。
「コード進行から~」なんて高説垂れすぎるのもアレなので、
全然違うアプローチのご紹介でした。
どんな方向を目指すかは貴方次第です、
様々な音楽を楽しみ、「こんなの作ってみたい!」を探してみてくださいね!
まとめ
今回は、テーマの次にコード進行を早い段階で決めておくとよい、
というお話をしました。
自分語りになってしまいますが、僕も最初はメロディから作ろうとしがちでした。
適当にメロディを打ち込み、「これじゃない!」ってなって捨てる、その繰り返しです。
それ以外にも足りないものはたくさんありましたが、
色んな理論や知識を貯めこんでいくと、かなり難しい所から始めていたんだなと思います。
理論無しで進めていくからこそ生まれるものもあったりするとは思いますが、
僕のようにそれだとロクなことにならないタイプの方も多いのではないでしょうか?
今回のお話がそんな方の役に立てたら嬉しいです!
それではオヤカマッサン!